〈社会契約論〉は、死刑を原理的に肯定するただひとつの根拠だ。〈社会契約論〉なら巷の死刑否定論に対抗できる。では、死刑を原理的に否定するには、どうすればいいか。新たな死刑否定論の構築に挑戦してみよう。
死刑で扱う〈死〉を私たちは知らない
罪を犯した者に〈死〉を与える死刑。そこには〈死〉という概念が含まれている。では、その〈死〉とはなにかを説明できるだろうか。いや、〈死〉そのものでなくてもいい。少なくとも現状の死刑において、〈死〉がどう扱われているか説明できるだろうか。
〈死〉は存在しない。〈死〉を私たちは知らない。そのことだけは知っている(「哲学者・池田晶子先生から「人生を考えるヒント」をいただく」)。刑罰として存在しているはずの死刑に〈死〉は存在せず、死刑の〈死〉を私たちは知らないのだ。
「なにゴチャゴチャ屁理屈を並べてるんだ。現に死刑囚は重い罪を犯しているのだ。社会にとって害悪なのだ。排除するのは当然だろう」。いささか暴論だけれども、そう思う人はいるだろうし、共感する人も、いまの日本には少なくないはずだ。
ホラー映画では死んだあとの世界が描かれている
ここでふたつの作品を参考にしたい。まずは、黒沢清監督によるホラー映画『回路』だ。人々が突然、黒い染みとなって消えてしまう現象が発生する。主人公のまわりの人たちもどんどんこの世から消滅していく。じつは、人は死んだあと幽霊となってあの世に行くが、そこは定員オーバーで、この世に幽霊があふれ出してしまっていた。幽霊たちは人が幽霊となるのを防ぐために、生きた人の存在そのものを黒い染みにして消してしまっているのだった。
回路 ©角川大映映画/日本テレビ/博報堂/IMAGICA 2001
もうひとつの作品は、白石晃士監督の『オカルト』。やはりホラー映画だ。とある観光スポットで無差別殺人事件が起こる。一命をとりとめた男は、それが神の“思し召し”だと思いこむようになる。最終的に男は渋谷の交差点で自爆テロを決行する。男は、自分や他人が死ねば理想郷のような場所に行けると信じこんでいたが、たどりついたのは、ただの地獄のような世界だった。
オカルト ©CREATIVE AXA Co.,Ltd.2009
〈社会契約論〉で〈死〉を扱うことはできない
〈社会契約論〉によれば、死刑を科しているのは私たち自身のはずである(殺人犯から見れば殺人犯自身)。しかし、私たちは〈死〉についてなにもわかっていない。だから、〈死〉を与えられた者がそのあとどうなるのかも知らない。
こんな想像はどうだろう。死刑になった者の行く“死後の刑務所”のような場所があるとする。そこはどんなところだろうか。『回路』で語られるように、すでに定員オーバーで、入りきれない者がこの世にあふれ出し、悪さをしていないとも限らない。もちろん、想像というよりむしろ妄想だが、そうでないという保証もない。
もっと悪い妄想もできる。殺人犯に殺された被害者も、(国家システムに殺された)殺人犯も、“死後の世界”に行くとする。殺人犯と被害者は、時間も場所も非常に近いところで死んでいるため、“死後の世界”で両者が出くわす可能性もある。そこで殺人犯はおなじ行為をくりかえさないだろうか。そこには殺人犯をつかまえる“警察”はいるのだろうか。
殺人犯と被害者の行く場所は別々であると妄想することはできる。いや、そう思わなければやっていられない。そもそもわからないのだから、どんな妄想もできる。だが、『オカルト』で描かれる“死後の世界”では、加害者と被害者の区別はない。平等に“地獄”を味わっている。死者という意味で両者はおなじであり、加害者と被害者を(たとえば神のような存在が)うまく判別してくれるとはかぎらないのだ。
どんなに楽観的な、あるいは恐ろしい妄想をしようとも、それが正しいことは永久に証明できない。たしかなのは〈死〉を私たちが自由に扱うことはできないということ。もちろん、国家システムでも同様だ。私たちはほんとうの意味で〈死〉を扱えない。にもかかわらず、〈死〉を刑として科してきたことで、恐ろしい結果をもたらしている可能性を否定できない。そう考えたら、軽々しく「死刑を科すのは当然」などとは言えなくなるだろう。
〈死の管理不可能性〉。これが、〈社会契約論〉にもかかわらず、死刑を否定する原理的な根拠となるのだ*注。
*注:当ブログが死刑を否定する根拠はほかに〈国家システムの抽象性〉があるが、これについては別の機会に述べたい。
ぎゃふん工房がつくるZINE『Gyahun(ぎゃふん)』

この記事は、『ぎゃふん⑩ 考えろ』に掲載された内容を再構成したものです。
もし『Gyahun(ぎゃふん)』にご興味をお持ちになりましたら、ぜひオフィシャル・サイトをご覧ください。




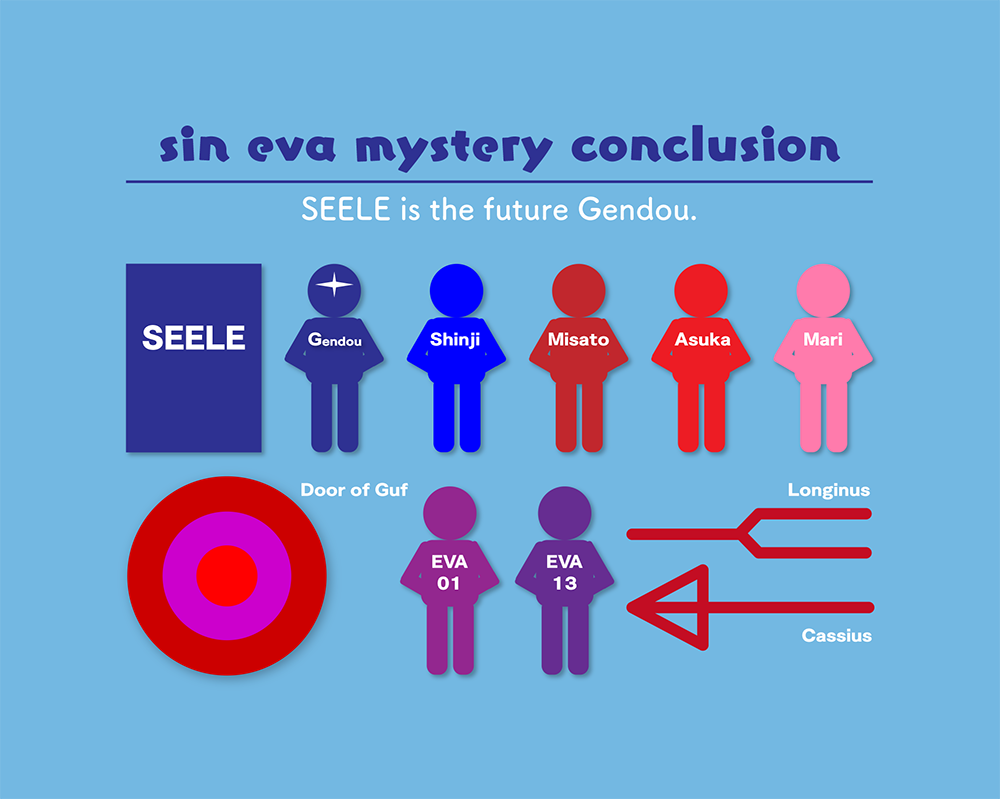


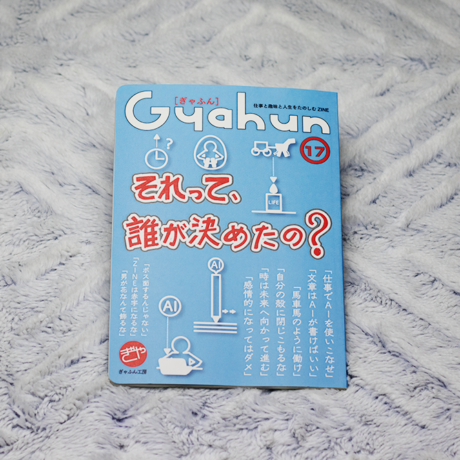
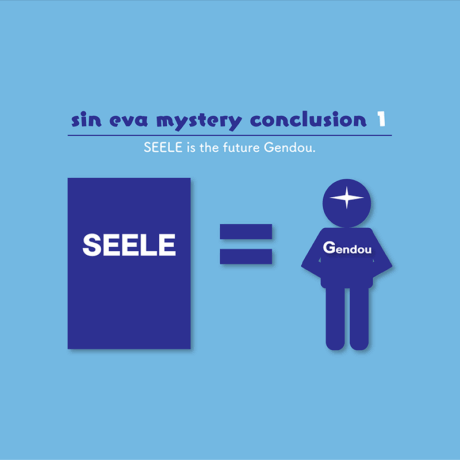
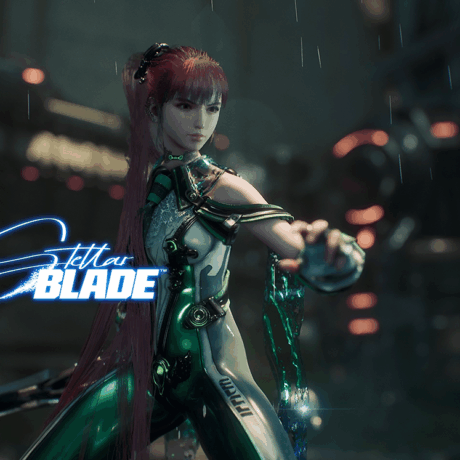

コメント