『バイオハザード ヴィレッジ』は最後に“ゾンビゲーム”だったことがわかる——。これには戸惑い・困惑・動揺をおぼえた。
なるほど、〈戸惑い〉か。
この〈戸惑い〉をキーワードにすれば本作の魅力を読み解けるかもしれない。
動画には暴力シーンやグロテスクな表現が含まれています。
ゲームをプレイする前から戸惑っていた
思い出してみると、本作の予告編を目にしたときから戸惑っていた。
『バイオハザード ヴィレッジ』Annoucement Trailer
まず、本作がVR(バーチャル・リアリティー)でないこと。前作『バイオハザード7 レジデント イービル』のレビューでこう述べた。
〈バイオハザード〉は、ゲームの発展とともに、その時代ごとに新しいホラー体験を提供するシリーズといえる。今後はVRがスタンダードになっていくのだろう。
本作ではVRを踏襲したうえで、さらに別のゲーム体験を与えてくれる。そう期待したのだが、それは裏切られることになった。
本作はFPS(ファーストパーソン・シューティングゲーム)。ありふれた様式だ。となると、そこから得られるゲーム体験・ホラー体験も凡庸なものになるのではないか? そんな危惧があった。
もうひとつ予告編で強く印象に残ったものがある。女の敵キャラクターたちだ。
これまでのシリーズにも、女の敵キャラは登場していた。女ゾンビは『2』にも出てくるし、『コード:ベロニカ』の最後のボスも女だ。けっして前例がないわけじゃない。
しかし、本作のようにバケモノでありながら、妖艶ないでたちで、知性を持ち合わせ、仲間や主人公とコミュニケーションをとるようなキャラクターはこれまでいなかった。
たんに女というだけでなく、一見すると〈バイオハザード〉に似つかわしくない怪しげな魅力を持ったキャラクターが現われる。
プレイする前から戸惑ってばかりだった。
ホラーゲームをプレイしている感じがしない
実際にプレイを始めると、〈戸惑い〉はより強くなった。
まずは“狼男”のような敵キャラの襲撃。〈バイオハザード〉シリーズでなじみのある「製薬会社のつくる生物兵器」のイメージからかけ離れていると感じた。“狼男”たちにもボスのようなポジションの存在があり、その下にザコがいるといった“序列”らしきものが見られる。これにも困惑。
ゲームの舞台も目まぐるしく変わっていく。雪にまみれたさびれた村から始まり、広大な城、心霊スポットのような屋敷、地下空間につくられた巨大な工場。やはりこれまでの〈バイオハザード〉とは趣が異なっているように思えた。
現実を模したリアリティのある世界というよりは、おとぎ話のなかに入り込んだような幻想的な味わいを感じる(冒頭の動く絵本のようなムービーはそれを象徴している)。
本作は「ホラー」というより「ダークファンタジー」といったほうが実感に近いかもしれない。
不気味さはあっても怖さはあまりない。過去作もシリーズによって恐怖度の大きさに差はあったが、必ずしも本格的なホラーを志向していない(と感じる)のは、本作が初めてではないだろうか。
これらの要素も、やはりプレイヤーをおおいに戸惑わせる。
〈戸惑い〉はやがて〈快楽〉に変わる
『バイオハザード ヴィレッジ』の制作陣が意図的にプレイヤーを戸惑わせようとしているのはまちがいない。ということは、本作は〈恐怖〉ではなく〈戸惑い〉をホラーのエッセンスとしていると考えられる。つまり、〈戸惑い〉こそがシリーズの伝統である「時代ごとの新しいホラー体験」になるわけだ。
そう理解することで、プレイヤーとしてどう本作に向き合えばいいのかわかった。〈戸惑い〉をおぼえるのは、プレイヤーの予想がはずれるから。この「予想がはずれる」ことは娯楽作品の王道のつくりだ。プレイヤーはおおいに戸惑い、困惑すればいい。
やがて〈戸惑い〉や〈困惑〉が〈快楽〉へと変わった。「今度はどんなふうに戸惑わせてくれるかな?」と期待するようになった。
ゲーム体験としてはじつに正統。良質なゲームだからこそ得られる至高の感覚といえる。
じつは〈バイオハザード〉らしさは守っている
「そうはいっても、〈バイオハザード〉っぽくないのは、いかがなものか?」。そういう声もあるかもしれない。
たしかに〈バイオハザード〉らしくない点に戸惑っているわけだが、冷静に分析すると、じつはこれまでのシリーズが築きあげてきた伝統を壊しているわけでもないのだ。
バケモノでありながら知性を持ち仲間や主人公とコミュニケーションをとる女といえば、前作のマーガレット=ベイカーがあてはまる(「妖艶」ではないかもしれないが)。“狼男”のようなモンスターも、第1作目のリメイクで「クリムゾン・ヘッド」としてすでに登場している。
つまり、けっしてシリーズのテイストからかけ離れているわけではない。
ゲームの舞台が目まぐるしく変わるのも、第1作目で私たちはすでに体験している。洋館が探索の中心になるにしても、終盤は研究所へ移動。『2』でも、警察署の探索を終えると、現実離れした巨大な研究所へと舞台を移している。
「ホラー」ではなく「ダークファンタジー」と感じるのも、プレイヤーの先入観とか既成概念にすぎない。従来のように「ウィルスに冒された人が次々とゾンビになる」設定も、リアルというより荒唐無稽。プレイヤーの「そういう悪夢がみたい」という願望を叶える“ファンタジー”ともいえる。
そんなふうに考えていくと、本作はじつに〈バイオハザード〉らしい。けっしてシリーズの伝統を壊しているのではなく、むしろしっかり踏襲しているのだ。
『バイオハザード ヴィレッジ』には“ゾンビ”が出てくる
本作はこれまでのどの作品よりもシリーズの伝統を踏襲している。
〈バイオハザード〉といえば「ゾンビの出てくるゲーム」というイメージが強い。これには多くの人が同意するはず。だが、『4』では「ガナード」と呼ばれるゾンビとは異なる存在が敵となり、『5』もそれを受け継いだ。『6』ではゾンビが登場するものの、敵の中心的な存在とはいえない。『7』ではゾンビはまったく登場しない。
本作でも、中心となる敵キャラは“狼男”などであって、やはりゾンビではない。
ところが——。
終盤で、ある衝撃的な事実が明かされ、プレイヤーはずっと“ゾンビゲーム”をプレイしていたことに気づかされる。
上記のリンク先にネタバレがあります。
もちろん、これまでのシリーズに登場するゾンビとは、見てくれもふるまいも異なる。だが、あらためて「ゾンビとはなにか?」を考えれば、だれもが納得するはずだ。たとえば——。
〈ゾンビ〉は死なない。すでに死んでいるから
本作が“ゾンビゲーム”であったという真実は、同時に前作をプレイ中になんとなくわきあがっていた違和感も解消する。前作の制作時にすでに考えられていたものなのか、それとも後付けなのかは不明だが、なかなかよくできた物語といえる。
まさに〈バイオハザード〉としての原点回帰。
最後までプレイヤーを戸惑わせてくれた『バイオハザード ヴィレッジ』。娯楽作品として、ホラーゲームとして「傑作」と評価することに“戸惑い”はない。
©CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED.
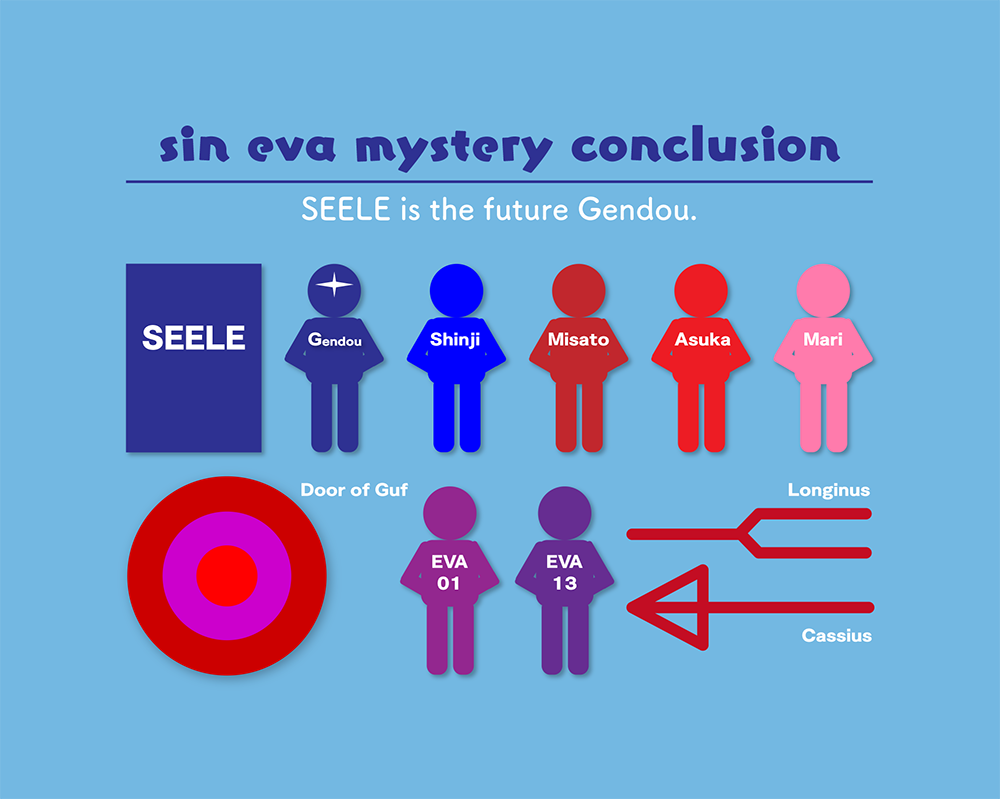

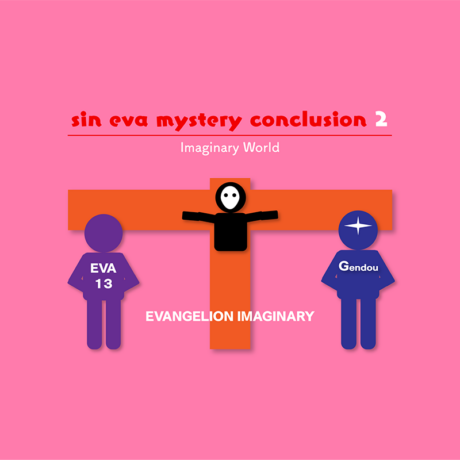
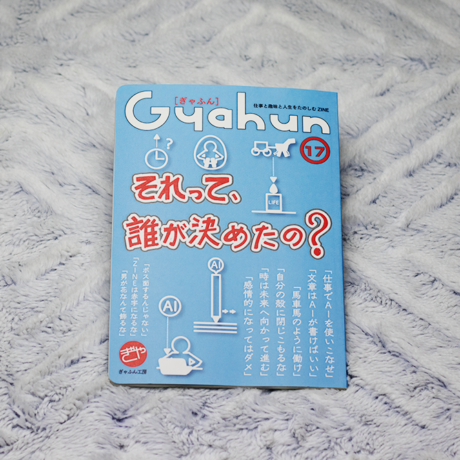
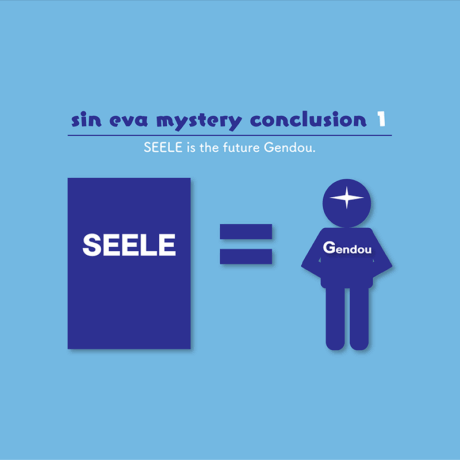

コメント