『ソウX』を観ていると、登場人物たちが残虐な拷問を受ける様をたのしんでしまっている自分に気づく。はたしてそんなことが許されていいのか? そんな悩みを抱くあなたに、本作を観賞しても道徳的・倫理的葛藤をおぼえないロジックを提供する。そう。思いっきり堪能してしまえばいいのだ!
[ネタバレなしで語ります。映画鑑賞前にもぜひどうぞ]
殺人鬼に肩入れしてしまうのは自然なこと?
本作のタイトル『ソウX』の「X」には「10作目」の意味があるらしい。「はて、自分はこのシリーズを10本も観たかな?」という思いが頭をよぎった。おそらく観てないはずだ。今回はそんなヤツのレビューだと思っていただきたい。
本作では、観る者はつい主人公のジョン=クレイマー(ジグソウ)に肩入れしてしまう。それはなぜか? という問題を考えたい。
ジグソウは殺人鬼であり、言うまでもなく、本来なら鑑賞者が応援したり自身を投影したりする存在ではない。なのになぜ? そんな自分の心の奥底にあるものを知りたい。
作品によってはダークヒーローに惹かれてしまうことはあるだろう。とくに本作は物語の序盤で詐欺集団への復讐という動機づけがなされ、鑑賞者がジグソウを応援したくなるよう巧みに誘導されている。それはあきらかだ。だから、ジグソウの味方をしたくなるのは必然。なんの不思議もないといえる。
ただ、「詐欺集団への復讐」という物語の端緒が一因だとしても、もっと本質的な、わたしたちがすぐには気づかない理由があるような気がしている。今回はそれを解き明かしたい。解き明かすことで、より深く本作を味わえる予感がするからだ。
〈ソウ〉シリーズの鑑賞者は残酷な人間なのか?
本シリーズはご存じのとおり、登場人物たちが目を覆いたくなるような拷問を受けるシーンに大きな特徴がある。さまざまな意匠や工夫を凝らした〈拷問装置〉が登場する。そこに本シリーズの魅力があるのは誰もが思い至る点だろう。
拷問装置およびそれらが動作するシーンは、はなはだ残虐である。にもかからず、魅力を感じ、嬉々として本作を観つづけてしまうのはなぜか?
鑑賞者であるわたしたちは、「これはあくまでフィクションだから」という自己弁護のもと、知らずしらずのうちにみずからのサディズムや嗜虐趣味を発揮してしまっているのだろうか。
それがゼロとはいえない。当ブログは専門家ではないが、だれもが多かれ少なかれサディズムや嗜虐趣味を持っているのではないか。
とはいえ、本作で展開されるような拷問シーンから自分は快楽を得ている、と素直に認めることもまた潔しとしない。ホラー好きであっても、そこまでの忌むべき嗜好を自分が発露させているとも思えず、したがって登場人物たちが受ける拷問は、作品の鑑賞であるにとってもまた“拷問”となる。
拷問装置の創造性に憧れているのか?
それでも、本シリーズに惹かれてしまうのは(そうだとわかってもつい観てしまうのは)、拷問装置の創造性(クリエイティビティ)に理由がありそうだ、と気づいた。
わたしたちは装置の残酷さをたのしんでいるのではなく、装置に創造性(クリエイティビティ)を見出し感心しているのではないか、と。そう考えれば、「僕は人が苦しむのを見たいんじゃあない。装置のクリエイティビティ、そこにシビれる! あこがれるゥ!」というわけだ。
これは、半分は自分に対する言い訳だとしても、あとの半分は真実のように思われる。
つまり、ジグソウ先生はそんなクリエイティブな人物だから肩入れしてしまう。先生の芸術をもっと見たい応援したい。そんな感情がわきあがるのだ。
僕たちはジグソウ先生に騙されたいのではないか?
そんなふうに思っていると、鑑賞者であるわたしたちも、ジグソウと同じ側、つまりダークな世界、闇の世界に堕ちていってしまう錯覚を覚える。本作からわたしたちが得ているのは、そんな自虐的な快感なのか。現実世界では体感できない、反社会的・反倫理的な世界に惹かれてしまっているのか。だから、ジグソウに想い焦がれるのだろうか……。
いずれもほんとうの正解ではないように思える。
本シリーズをよく思い返してみると、拷問装置のクリエイティビティに目を奪われてあまり意識しないのだが、ジグソウの創造性が発揮されるのは、その装置の意匠(デザイン)だけではないことがわかる。
(ここからはネタバレを避けるために、ややボカした書きかたになるが)本シリーズを観ている最中「うわっ、やられた!」という声が思わず出てしまう瞬間がある。「まんまと制作陣にしてやられた」という悔しさをおぼえる——というより感服してしまうことが多い。
フィクション世界の外から見れば、一枚上手なのは作品の制作陣になるが、劇中では仕掛けているのはジグソウだ。ジグソウの思惑に、鑑賞者たるわたしたちが騙されてしまう、手のひらで躍らされてしまう。
本シリーズでは、劇中の人物であるダークヒーロー(主人公)と制作陣の思惑が完全に一致している。そこが特徴かもしれない。そういつくりになっている作品は、意外に少ないのではないか(探せばあると思うが、すぐには思い浮かばない)。
「僕たちはジグソウ先生に騙されたい」。これがわたしたちの自分でも気づかない秘めた欲望なのではないか。本シリーズではそんな欲望が引き出されてしまうのだ。ちょっと歪な快感とともに——。
©2024 Lions Gate Ent. Inc. All Rights Reserved.
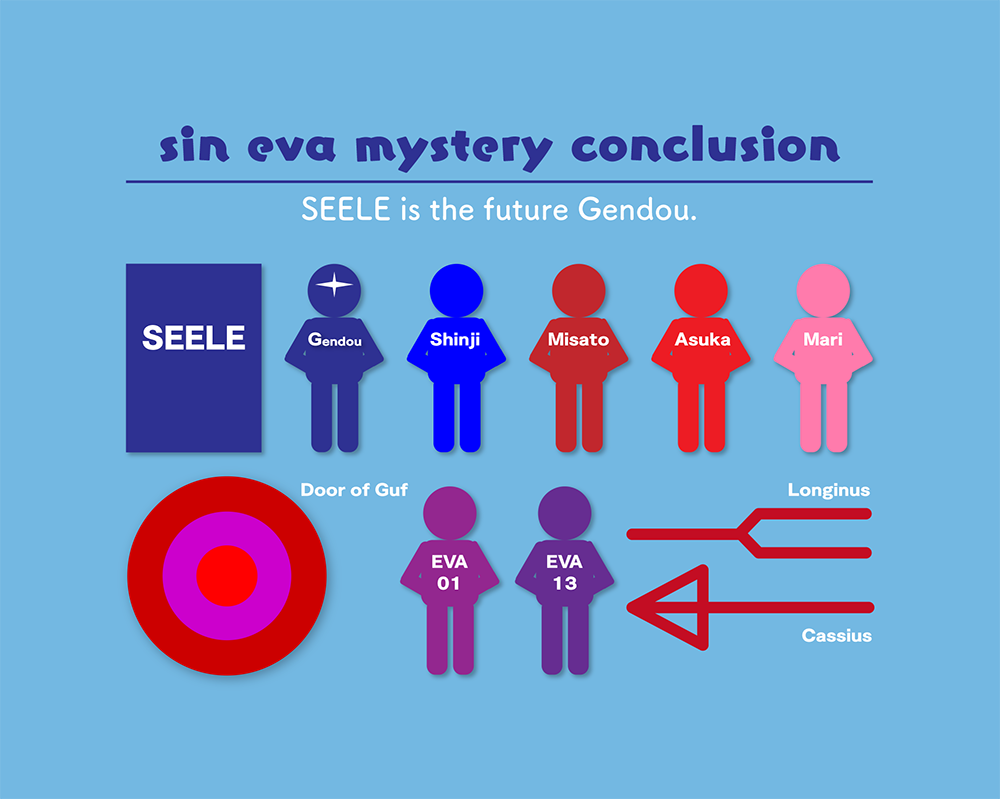


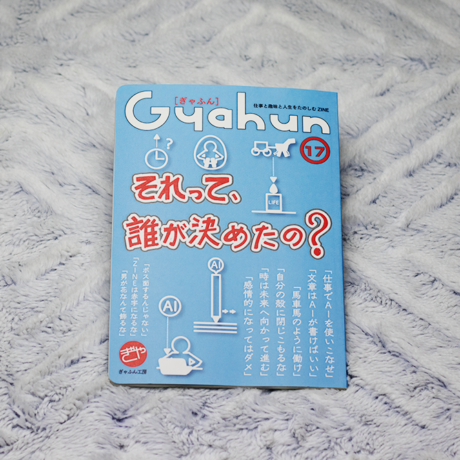
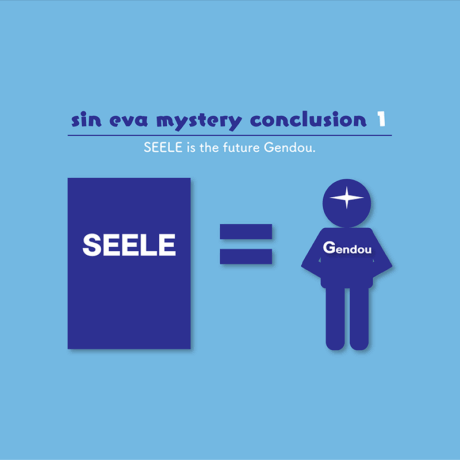

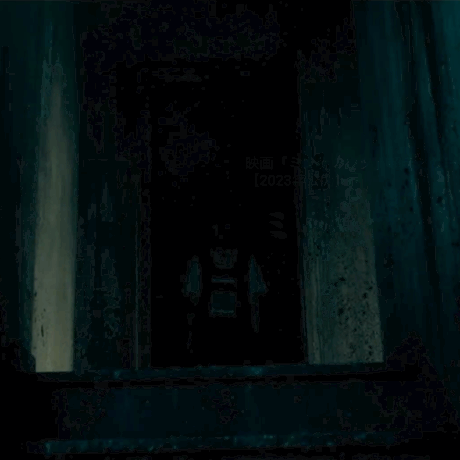
コメント