日本で暮していて〈ウルトラマン〉をまったく知らずに生きていくのは難しいでしょう。私も子どものころに“つまみ食い”した憶えがありますし、大人になってからも『ウルトラマンオーブ』を楽しく視聴しました。
とはいえ、〈ウルトラマン〉に対してあまり思い入れはありません。本作『シン・ウルトラマン』も「AmazonのPrime Videoで配信されたら観ればいいか」などと考えていました。
映画館に足を運ぶ気になったのは、『特報』を観たのがきっかけです。
映像の最後に、ウルトラマンがスクッと立ち上がります。それが妙に印象に残りました。ただ立ち上がるだけなのに、なぜか琴線に触れたのです。
そこに本作の魅力を読み解く鍵がありそうです。
ウルトラマンは〈人〉じゃない
「ウルトラマン」をむりやり漢字で表わせば「超人」でしょうか。つまり「人を超えるモノ」。どの部分が「人を超える」かといえば、端的にいえば体の大きさです。空を飛んだり光線を出したりもしますが、やはりウルトラマンのアイデンティティは「巨人が怪獣と戦う」ところにあります。
大きさが〈人〉を超える一方で、挙動は〈人〉と変わりません。もし私たちがなんらかの理由で巨大化し、怪獣と取っ組み合いをしたら、ウルトラマンと似た動きになるはずです。ウルトラマンはスーツを着た役者が演じています。動きが〈人〉と変わらなくても不思議ではありません。
でも本作『シン・ウルトラマン』のウルトラマンは、ふつうの〈人〉とは微妙に異なる動きをしている。そこがポイントなのです。
本作のウルトラマンはCGでつくられているそうです。たとえば、怪獣(本作では「禍威獣」)の攻撃が命中し体が吹き飛ばされても、ウルトラマンは地面に叩きつけられるのではなく、紙でつくった人形のようにフワッと着地します。まるでこの世界の物理法則を無視するかのように。クライマックスの“大爆発”に巻きこまれるシーンでは、あたかも意思を持たないフィギュアのように爆風に翻弄されます。つまり、挙動がほかのウルトラマンと異なっているのです。
ウルトラマンが「人を超えるモノ(=超人)」であるならば、ようするに〈人〉ではないのですから、挙動が〈人〉とは異なっていても問題はないはずです。いや、むしろほかのウルトラマンのほうが不自然であるとさえいえます。
「ウルトラマンは〈人〉じゃない」。この当たり前の真実を本作は追究しているのではないでしょうか。「ウルトラマンは〈人〉じゃないから、動きかたも〈人〉とちがうほうがいいよね」という答えに制作陣はたどりついたのでしょう(*注)。
『特報』のウルトラマンの立ち上がる姿が印象に残った理由も、いまならわかります。「〈人〉のカタチをしているけれど〈人〉ではない」動きを再現していたからなのです。
「人を超えるモノ」の動きを表現することによって、役者がスーツを着て演技するのとは異なるダイナミズムが生まれます。〈人〉とはちがう挙動に対する違和感が観る者に奇妙な快楽をもたらすのです。監督・樋口真嗣氏の手腕がいかんなく発揮された結果といえそうです。
*注:「ウルトラマンの見た目はCGだけど、挙動は役者の動きをモーションキャプチャーしているぞ」というツッコミもおありかと思います。モーションキャプチャーは、〈人〉ではなく、〈人のカタチをしたモノ〉の動きを表現するためのものと勝手に想像しています(たとえば、関節は人とおなじ方向に曲がる、など)。
ウルトラマンとは何モノなのか?
「ウルトラマンは〈人〉じゃない」。この点はウルトラマンの挙動だけでなく、物語においても追究されています。
「〈人〉ではないウルトラマンとは、どういう存在なのか?」。そんな疑問を本作は投げかけます。でも、簡単に答えの出せるものではありません。
そこで、本作『シン・ウルトラマン』は、「ウルトラマンとは何モノなのか?」の疑問に答えるために、あえて回り道をして「〈人〉とは何モノなのか?」と問います。〈人〉を定義づければ、「ウルトラマンは〈人〉の定義を超えるモノ」と、とりあえず理解できます。
といっても、本作は「〈人〉とは何モノなのか?」をテーマの中心にすえているわけでもありません。終盤の一場面でちょこっと触れられる程度です。観る者に対し「おまえは何モノなのだ?」などと説教はしません。
それでも観ている側は、「外星人であるウルトラマンから見ると、私たち〈人〉はどういう存在なのか?」と、あらためて自分自身を見つめ直さざるをえなくなります。ウルトラマンの活躍ぶりを観ていたはずが、いつの間にか自分自身に意識が向いているのです。
本作は巨人が怪獣と戦う荒唐無稽な〈虚構〉であるはずなのに、いつしか自分のいる〈現実〉と融合してくるような、そんな奇妙な感覚をおぼえます。なにやら深遠なテーマの香りがスクリーンの向こう側から漂ってくる。これも本作の魅力といえそうです。
「虚構と現実の融合」。私の好きなコトバです。脚本の庵野秀明氏もきっとお好きでしょう。

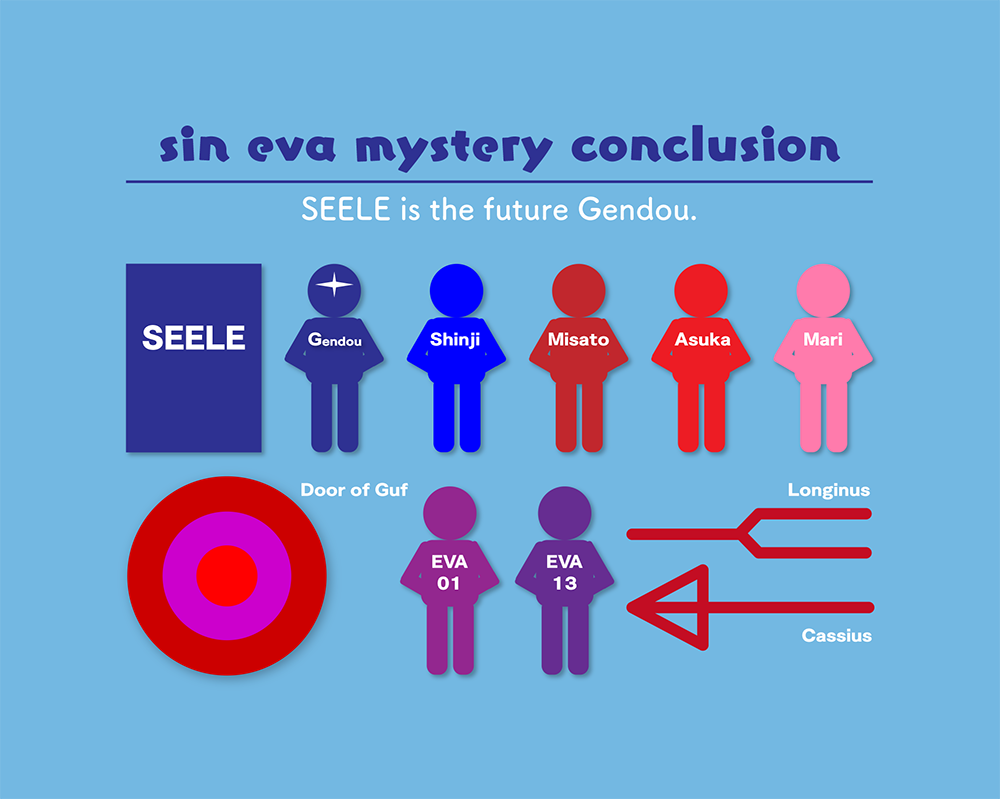


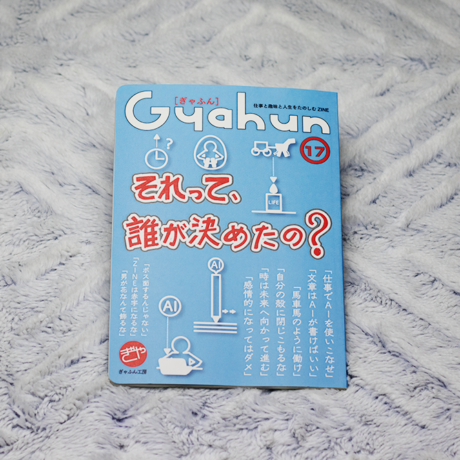
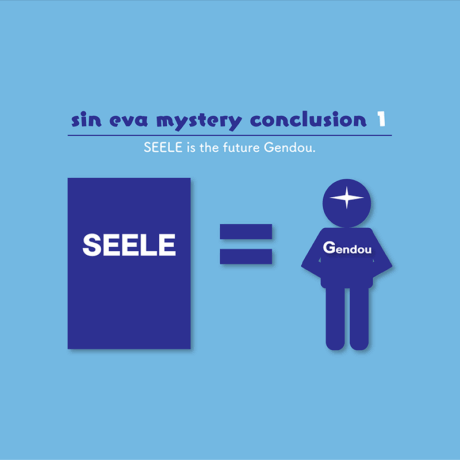
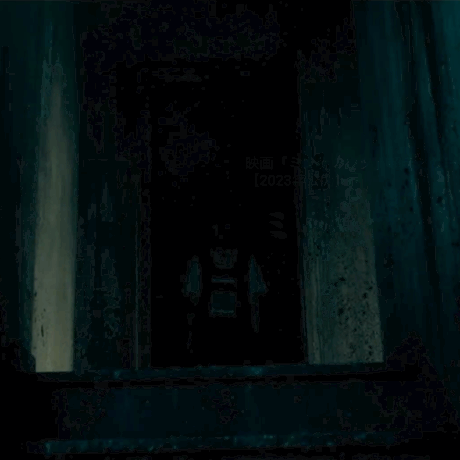
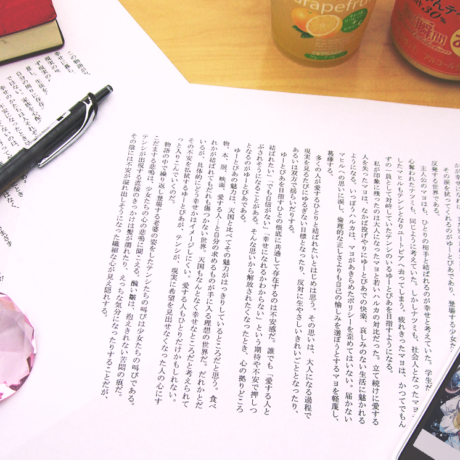
コメント