〈ラクーンシティ〉を訪れるのは、この『バイオハザード RE:2』で4度目になる。『バイオハザード2』『バイオハザード3』『バイオハザード オペレーション・ラクーンシティ』と、いままで大量の〈ゾンビ〉を撃退した。アンブレラ社が送り出す、より強力な〈B.O.W.(生物兵器)〉さえも亡きモノにしてきた。その自負がある。
「もはやゾンビなんてチョロい」「リッカーなんて、その攻略法も知り尽くしている」「追跡者。来るとわかっていれば怖くない」。そう高をくくっていた。
「グラフィックやサウンドといった表現は、最新の技術でこれまでより強化されているだろう。また、ゲームシステムがTPS(サードパーソン・シューティングゲーム)になったことで、前とは異なるプレイ感覚を味わえるだろう。本作ではそれを存分に堪能すればいい。レジャー感覚で愉しめばいい」。STARTボタンを押すまで、そう考えていた。
しかしながら——。
それが、あさはかな考えだったことを、プレイ開始わずか数分で思い知らされる。
けっして甘くはなかったのだ、アンブレラ社製〈ゾンビ〉は。やはり良くも悪くも“一流”の企業だった。
これから語っていこう、ゲーム中に体験した“悪夢”について。そして、悔い改めよう、その膨れあがった慢心を……。
もくじ
アンブレラ社製〈ゾンビ〉が真の恐怖をもたらす

〈バイオハザード〉シリーズは、ゾンビゲームの代名詞だ。本作の“悪夢”をひもとくために、まずこの〈ゾンビ〉に着目してみよう。
〈ゾンビ〉は死なない。すでに死んでいるから
本作をプレイする者の多くが——いや全員が最初に恐怖のドン底に落とされるとき。それはまさに1番めに登場する〈ゾンビ〉と対峙する場面だろう。
頭部に照準を合わせヘッドショットを決めていくが——倒れないし、死なない。そして、やすやすと主人公への接近を許し、喰われてしまう。バ・カ・な。オレは百戦錬磨のホラーゲーム・プレイヤーなんだぞ!? 気づくと、コントローラーを持つ手が震えている。いまのはケアレスミス。たまたま調子が悪かっただけ。ノーカン、ノーカン。〈バイオハザード〉シリーズは、老若男女が楽しめるよう難易度が調整されたゲームだ。苦戦などありえない……。
だが、プレイをつづけているうちに、ケアレスミスでも、単なる不調でも、あまつさえ制作陣が幼稚園の先生のような“やさしさ”にあふれていたわけでもなかったことを知る。
本作の〈ゾンビ〉は死なない。だって、すでに死んでいるから。
もちろん、ありったけの弾丸をブチこめば、二度と起きあがれないようにすることは理論上は可能だ。しかし、入手できる弾はかぎられている。〈ゾンビ〉はそこらじゅうにウジャウジャいるのだ。殲滅することなど、実際には無理。とはいえ、ヒーローを気取らず、恥も外聞もプライドも捨て〈逃げ〉に徹することで、この問題はいちおう解決できる。
もっと重要なことが別にある。なんとか倒したとしても、ほんとうに死んでいるのか、不安にならざるをえないことだ。死体はどんなに時間が経過しても消えることはない。まして何発か弾を食らうと、いったんは床に倒れるから始末に負えない。
マニュアルはこうアドバイスする。
ゾンビの生死を見分けるのは難しい。
疑心暗鬼にとらわれたなら、ナイフで確認すると良い。
そういう問題じゃないんだ! ナイフで斬りつけたとき、もし生きていたら起きあがってくる。そんなことには耐えられない。かりに生きていなかったとしても、「起きあがってくるかもしれない」。そう思ってしまうことが受け入れられないのだ。
〈死〉そのものが迫ってくる恐怖に直面する
〈ゾンビ〉を嗤う者は、〈ゾンビ〉に泣く。相手を見くびっていたことは猛省しよう。初心に返ることもしよう。それにしてもこの恐怖感はただごとではない。いったいどうなっているのか? その分析を試みる。
最初は、〈敵意を持った存在が迫ってくる〉から怖いのだと思った。〈ゾンビ〉の造形というより、むしろその裏側にある〈負の感情〉ともいうべきものに恐怖しているのだ、と。
ただ、それは『バイオハザード4』をプレイしたときに感じたこと だ。たしかに、『4』の敵である〈ガナード〉には当てはまる。だが、本作の〈ゾンビ〉は少しちがう。「敵意」を持って襲ってきている気はしない。
では、本作をプレイしているときに覚える、とてつもない恐怖感の正体はなんなのか?
ゾンビ映画をレビューしているこちらの記事で、〈ゾンビ〉の本質についてこう述べた。
本作(『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド/死霊創世記』)の〈ゾンビ〉たちは、目が光ったり、口から長い舌が伸びたり、手から鋭い爪が生えたりはしない。つまり死体以外の何物でもない。死体とは、すなわち死の象徴だ。本作では、「ゾンビに殺される恐怖」と「死そのものが迫ってくる恐怖」を同時に味わうことになるのだ。
ここでいう映画の〈ゾンビ〉の本質こそ、本作の〈恐怖〉の正体なのではないか*注。
*注:ちなみに、おまけコンテンツには、「目が光ったり」する〈ゾンビ〉も登場する。
では、なぜ「死そのものが迫ってくる」ことに、これほどまでに強烈な恐怖を覚えるのか。
それは、〈死〉が不条理なものだからだ。われわれは〈死〉を理解しているように錯覚しているが、じつはなにもわかっていない。なおかつ、そのことを自覚していない。
前述のとおり、本作の〈ゾンビ)は敵意を持っているようには思えない。なのに襲ってくる。まさしく、そこが不条理。わけがわからない。そこに恐怖する。対照的に、〈ガナード〉がなぜ襲ってくるのか、あるていどは理解できる。そのぶん恐怖は薄れる。
本作の〈ゾンビ〉は、これまでのシリーズはもちろん、ほかのホラーゲームでも表現されていなかった新しい〈恐怖〉のカタチといえる。これこそ、われわれがいままで知るよしもなかったアンブレラ社製〈ゾンビ〉の真実だったのだ。
ゾンビ[も]出てくる、ゾンビ[が]出てくる
〈バイオハザード〉シリーズを「ゾンビが出てくるゲーム」と表現しても反対する人はいないだろう。ゲームの内容を端的に表わしているのはまちがいない。
しかしながら、ここであらためてシリーズを振りかえってみる。ゲームの目的は、迷いこんだ洋館からの脱出であったり、極限状態におかれた場所からの逃亡であったり、悪徳企業の野望を打ちくだくことだったりする。〈ゾンビ〉は、道中に立ちはだかる“障害物”のようなもの。〈ゾンビ〉の撃退は、目的を達成するための手段であり、目的そのものではないわけだ。
また、シューティングゲームとしては、〈ゾンビ〉は射撃の爽快感を味わうための的のようなもの、という見かたもできる。
つまり、「ゾンビが出てくるゲーム」ではなく「ゾンビも出てくるゲーム」のほうが、より正確な表現ともいえるのだ。
そこを本作の制作陣はあくまで「ゾンビが出てくるゲーム」として創ることにこだわった。〈ゾンビ〉がもたらす圧倒的な存在感と恐怖感は、そこに理由があると考えられる。
実際、〈バイオハザード〉シリーズには〈ゾンビ〉の登場しない作品も多い。ここへきて、名実ともにゾンビゲームの代名詞にふさわしい作品に昇華したのだ。
異形がはびこる街で真の〈サバイバルホラー〉を体感する

〈ゾンビ〉の異様なまでの存在感と恐怖感。その実現にこだわった制作陣。これだけでも、本作は評価に値しよう。自分のゲーム選びはまちがっていなかったと、満足感に浸れる。
とはいえ、〈ゾンビ〉に着目するだけでは、なにかが欠けている気がする。その正体もつきとめておきたい。
探索をする勇気がくじかれる
プレイ開始後しばらくしてそいつが現われたとき、〈ゾンビ〉とは異なる〈恐怖〉をプレイヤーは味わうことになる。
「オレは過去にこいつと出会っている。強敵であることも知っている。だから、対処法も心得ている。そう。逃げるんだよ〜」などと余裕をかましていると、またしてもわれわれの精神は奈落の底へと叩きおとされる。過去の作品をやりこんできた猛者を自称するプレイヤーほど、立ちなおれない。古びた戦法はそいつには通用しない。
そいつのふるまいは、プレイヤーにとって重大な問題を引きおこす。そこでまた恐怖する。その問題とは——。
じっくり探索できない
ということ。
ゲームを先に進めるためには、アイテムを探し出し、しかるべき場所で使用して活路を見出さなければならない。このゲーム性はシリーズを踏襲している。
そのアイテム探しの前提となる〈探索〉がじっくりできない……いや、その勇気が出ない。プレイ中、動悸はおさまらない。
プレイヤーにとってこれは致命的。立つ瀬がない。
主人公は建物のなかで、つねに走りつづけなければならない。足を止めたら、それは〈死〉に直結する。
「なぜ、制作陣はゆっくり探索させてくれないの? バカヤロー!」と思わず悪態をつきたくもなる。
だが、よくよく考えてみると、こんな極限状態で「ゆっくり」できていた、これまでのシリーズのほうがむしろ不自然だったのだ。〈死〉が迫りくる状況で、落ちついていられるほうがおかしい。
ゾンビ映画では、登場人物が焦りのあまり大事なモノを落としたり、つまずいて転んだりする場面がある。観ている側は「なにしてんだよ!」とツッコミを入れながら、「わかる。その気持ち」と共感する。
プレイヤーは、まさにそんな映画の登場人物とおなじ状態に陥ってしまう。自分たちが“笑われる”立場になってしまう。制作陣のほくそ笑む顔が目に浮かぶようだ。
〈サバイバルホラー〉の真の意味を思い知る
ここでわれわれは〈サバイバルホラー〉のほんとうの意味を知ることになる。すなわち、〈サバイバルホラー〉とは、
精神的動揺を余儀なくされる極限状況で、かぎられた資源を最大限活用しながら、生き残りを図る
ことだ。
本作において、弾があまり手に入らなかったり、武器がパワーアップできなかったりするのも、〈サバイバルホラー〉であるため。
まっとうなゾンビ映画なら、登場人物たちに「積極的に戦う」という選択肢はない。強力な武器でバケモノを一掃できてしまうのは、邪道。本来の〈サバイバルホラー〉ではない。
ヘッドショットで撃退できない〈ゾンビ〉に心の底から怯えてもいいじゃないか。コート姿の大男を見かけた途端、踵を返してセーブ部屋まで舞いもどってもいい。舌の長い異形から逃げまわるばかりで正面からやりあう勇気が持てなくても。すべて許される。それこそが〈サバイバルホラー〉におけるプレイヤーのあるべき姿なのだ。
もっとも強い敵こそがもっとも哀しい

本作の最強の敵は、〈G〉と呼ばれるバケモノ——のはずなのだが、なぜか〈G〉が登場すると安心感を覚えてしまう。「よう、また会ったな、バーキン」とあいさつをしたくなる。
〈G〉が襲ってくる前に弾を補給させてくれるので、戦いにしっかり備えられる。現場にも物資がそこかしこに置かれているから、戦いながら拾いあつめていけばいい。あとは、なにも考えず、ひたすら弾を相手に当てていく。すると、意外にあっさり撃退できてしまう(難易度が「STANDARD」の場合ではあるが)。攻略法を見つけるために試行錯誤する必要はない。
本作における〈恐怖〉の本質は、「不条理な〈死〉そのものが迫ってくること」であり「極限状況で生き残りを強いられること」。前述したとおりだ。
〈G〉の存在は『2』をプレイしていれば十分に理解できるものだし、『2』を知らなくてもゲーム中に説明されるからわかる。少なくとも不条理とまではいえない。十分な武器を持った状態で戦いに挑むから、〈サバイバル〉感もほとんどない。
したがって、ボス戦がもっとも怖くない。なんとも皮肉な話だ。
もちろん、これは欠点ではない。キャラクターに深みが出て、作品として味わい深いものを感じる。
その点は制作陣も意図しているのか、〈G〉に変化したバーキンは“畏怖すべき相手”ではなく、“憐れむべき存在”として表現されているようにも思う。
たしかに、恐るべき兵器を開発した事実に対して道義的・倫理的責任はまぬがれないだろう。いわば“罰”を受けたカタチで決着するのもやむをえまい。だが、バーキンは本気で殺人の道具をつくろうとしたのではなく、純粋に科学者としてみずからの野心を追究しただけなのではないのか? そんな人間像が浮かびあがってくる。
プレイヤーとして当ブログは、〈G〉に敵意は向けなかった。というより同情した。トドメを刺すときも、主人公たちのように罵るコトバは吐かなかった。口にしたのは「神のご加護を……」だ。
われわれもアンブレラからは極悪非道の仕打ちを受けたのだ。バーキンの無念は痛いほどわかる。むしろ「同志」と呼ばせてほしい。結果的には敵対することになってしまったが、状況がほんの少しちがっていれば、共闘してアンブレラを打倒できたのかもしれない。アネットも救えたはず。シェリーの運命だって変えられたにちがいない。
本作で体感する感情は〈恐怖〉だけではなかった。これは予想外。
そんな不運な家族に想いをはせながら、ここでいったんコントローラーを置くとしよう。
神のご加護を……。
ⒸCAPCOM CO., LTD. 1998, 2019 ALL RIGHTS RESERVED.




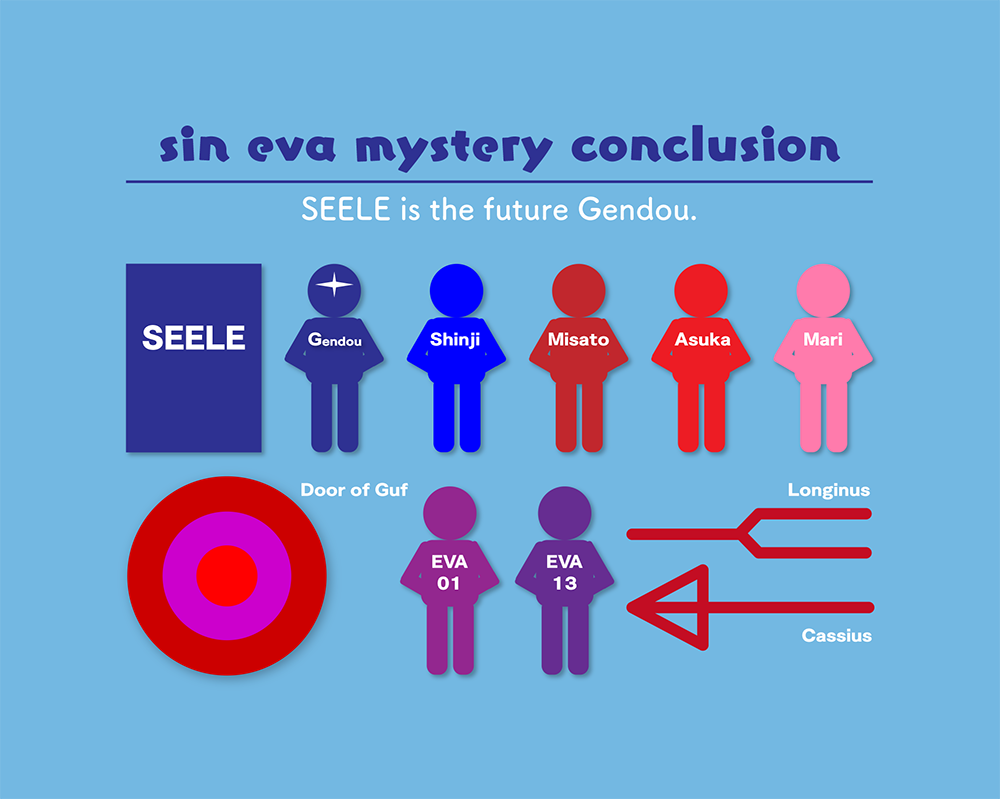


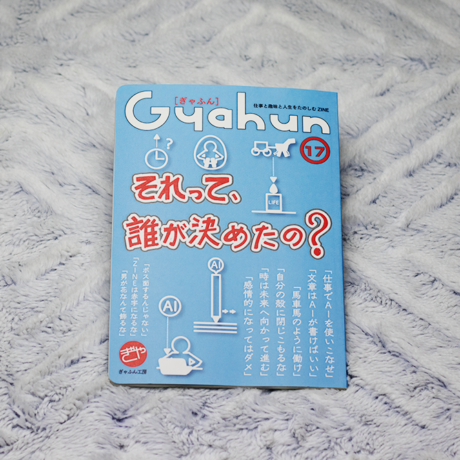
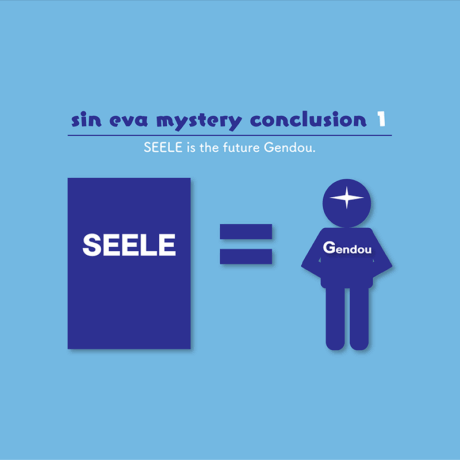


堪能しているようですね。
私は、難易度スタンダードは全てS+ランクでクリアして、
難易度ハードコアはレオンとクレアの裏がまだAランクなどです。
シリーズファンとしては、
初回プレイはハードコアで始めるべきだろうと思って始めたら
クリア時間が10時間以上でした。
北米版と比べると欠損規制がありすぎて
ゾンビをクリティカルヒットで倒しても良く分からないのが玉に瑕だと感じました。
やりこんでいらっしゃいますね。世間の評判もいいようですね。
表現の規制はあまり気にしていませんでしたが、ゲーム性に関わってくるとなると、ちょっと問題がありますね。
コメントありがとうございました。