『バイオハザード RE:4』は、『RE:2』や『RE:3』よりもおもしろいと感じた。
なぜ本作『RE:4』の出来栄えは他の2作よりもよかったのか? いや、なぜ私は『RE:4』をおもしろいと感じたのか?
今回はその謎を解きあかす“思索の旅”に出ようと思う。
『バイオハザード RE:4』は「怖い」とか「難しい」ではなく「おもしろい」
〈バイオハザード RE〉シリーズに対する私の向きあいかたはこうだ。
最新のゲームとはいえ、リメイク作であり、つまりは原作を遊んだ経験があるわけだから、とりあえずは昔と今のちがいを愉しむ。昔と比べて〈世界〉は鮮明かつ深みをもって構築されているだろうから、より高度なゲーム体験を堪能する。
ゲームの目的は何者かによって拐かされた大統領の娘を救い出すことだが、物語が始まる前から彼女の居場所を私は知っている。最初に訪れる村では住民たちが自分を暴力的な方法で出迎えてくれることもわかっている。
未知なるものへの期待や不安ではなく、既知への憧憬。それが〈RE〉シリーズをプレイする際に持つべき心構えである——というのが永年にわたるゲーマー人生の経験から導き出された結論だった。
実際にプレイをスタートし、現地の警官の案内で最初の村に足を踏み入れる。“昔”とは少しばかり様子が異なっており、1人目の村人のふるまいや、警官たちの行く末もちがっている。そこにいささか不安をおぼえ緊張もするが、恐怖を感じるほどではない。予期していなかったとしても想定外ではないからだ。
〈世界〉は再構築されているものの、イチから建てなおしたのではなく、いわばリノベーション。内装に手が加えられているだけだ。面影はあちらこちらに残っているから、安心感すらおぼえる。
このまま不安感と緊張感と安心感がほどよくブレンドされた味わいを満喫すればいい。
そう思っていたのだが……。
「ん? なんかちがう!?」
最初に違和感をおぼえたのは、娘を助け出したあと、村人たちに取り囲まれ小屋に立てこもる局面だった。“昔”もここは難所であり、覚悟して臨んでいた。実際、何度かゲームオーバーになったが、なかなか先に進めないことに違和感があったわけではない。
「おもしろい……だと?」
「怖い」とか「難しい」ではなく「おもしろい」。意外な感情が強くわきあがってきたのだ。
「いいことじゃないか。ゲームなんだから」
たしかに。ゲームがおもしろい。これ以上の悦びがあるだろうか。本作を選んだ私は正しかった。なけなしのお金で本作を買い、貴重な時間をプレイに費やす。その価値があったのだ。まさに人生の勝利。
もしも私がふつうのゲーマーだったなら「万事OK」「首尾は上々」といったところだ。
しかし、私はゲームの感想文を40年近く書きなぐっている“異端児”。理解しがたい感情の正体を突きとめねば、平穏に生きてはいけない。
『バイオハザード RE:4』はなぜおもしろいのか。その理由を追究せずに、本作のレビューを終えることはできないのだ。
『バイオハザード RE:4』の魅力は〈戦術性〉の高さ
本作には、ところどころ難所が設けられており、一回のプレイでは突破できない局面がある。もちろん、これはアクション・シューティングとしては王道のつくりだ。というより、まったく苦労もなしにプレイできてしまうようなら、歯ごたえがなく、「おもしろい」とは思えないだろう。難所そのものは、それこそ『RE:2』や『RE:3』にも見受けられる。だから、そこが肝心なのではない。
「じゃあ『RE:4』はなにがちがうの?」
本作は他の2作とは異なり、闇雲にプレイしていてはクリアできない。いいかえれば、『RE:2』や『RE:3』は何度か挑戦しなおせば突破できる。敵の攻撃パターンがなんとなくわかれば、活路は見出せるからだ。
一方、『RE:4』は「なにも考えずに攻撃していると敵に太刀打ちできない」ことに気づく。つまり、「しっかり戦術を立ててプレイしないとクリアできない」のだ。敵の攻撃パターンをつかんでも、それだけでは難関を突破することには結びつかない。ようするに『RE:4』は「〈戦術性〉が高いゲーム」といえる。
「なんで〈戦術性〉が高いとおもしろいんだろう?」
そこだ。そこに本作の真髄がある。〈戦術性〉に気づく前、私は難所を次のように乗り越えようとした。
無数の敵の猛攻をショットガンで蹴散らしたり、三方が壁に囲まれた場所に陣取り狙い撃ちしようとしたりしたのだ。原作ではこのやりかたが通用したし、他のゲームでも盤石な攻撃法だろう。
ところが、本作ではダメ。あっさり返り討ちにされてしまう。途中で、この戦法は効果的でないことに気がついた。
ハンドガンで一体ずつ丁寧に捌いていくほうが生存率は高い。「敵をしっかり狙って撃つ」という、王道の戦いかたこそがもっとも有効だったのだ。
安直にショットガンで敵をまとめて葬ろうとしたり、有利な場所に逃げこんで手軽に撃退しようとするようなマネは、〈戦術性〉が高いとはいえない。本作のゲームデザインは、そんな“ズル”を許さないのだ。
状況を的確に見極め、愚直に行動して、道を切り拓いていく。すると、努力が実る達成感、思惑が当たる爽快感を得られる。
それこそが『RE:4』の魅力だと私は考えている。
敵意を持って襲いかかる相手を撃ち負かすという“快楽”
『バイオハザード RE:4』のおもしろさの秘密は〈戦術性〉にある。そこまでわかれば十分だったかもしれない。しかし、なにかを見落としている気がする。たとえるなら、せっかく鍵を拾ったのに宝箱を開けないまま先に進んでしまったような“やり残し感”。
モヤモヤした気持ちを解消するヒントは、それぞれに登場する〈敵〉にありそうだ。
『RE:2』『RE:3』の敵はゾンビ。『RE:4』はガナードだ。両者のちがいはどこにあるのか? それは〈敵意〉の有無ではないかと思う。
ゾンビはプレイヤーに襲いかかってきても、そこに敵意はないように思える。というより、ゾンビは“死者”であり、感情を持っているようには見えない。一方、ガナードは、ふつうの人間ではないとはいえ、理性や感情は残っていると想像できる。したがって、プレイヤーを殺そうとする行動に敵意や殺意を感じる(設定上は何者かに操られてはいるのだが)。
敵意を持たないゾンビを撃ちたおしても、縁日の射撃ゲームで的に弾を当てるのとおなじで、それほどカタルシスは得られない。一方で、敵意を剥き出しにして襲いかかるガナードを倒せば、「返り討ちにしてやったぜ」というドス黒い快楽をおぼえる。
本作が『RE:2』や『RE:3』よりもおもしろいと感じたほんとうの理由はそこにある。
本作の表面にある〈戦術性〉という皮を一枚はがしてみると、裏側にはプレイヤーの非人道的・反倫理的な負の感情が見出せてしまう。
「『おもしろい』と感じたのは間違いだったのか?」
わからん。わからなくなってきた。“正当防衛”とはいえ、嬉々として銃を向け、あまつさえ撃ち殺してしまったことは事実。相手は理性や感情を持った人間なのに……。
本作の主人公とヒロインの体に寄生虫が巣くったように、いつしかプレイヤーにはゲームを通して忌むべき感情が注入されていく。物語の終盤、主人公たちの寄生虫は無事に取り除かれるが、私たちはドス黒い感情という“寄生虫”を宿したままゲームを終える。
その真実に気づいてしまったことで、「おもしろい」ではなく「怖い」という感情がわきあがる。
私の平穏な生活は遠のいてしまったようだ……。
動画には暴力シーンやグロテスクな表現が含まれています。
©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.


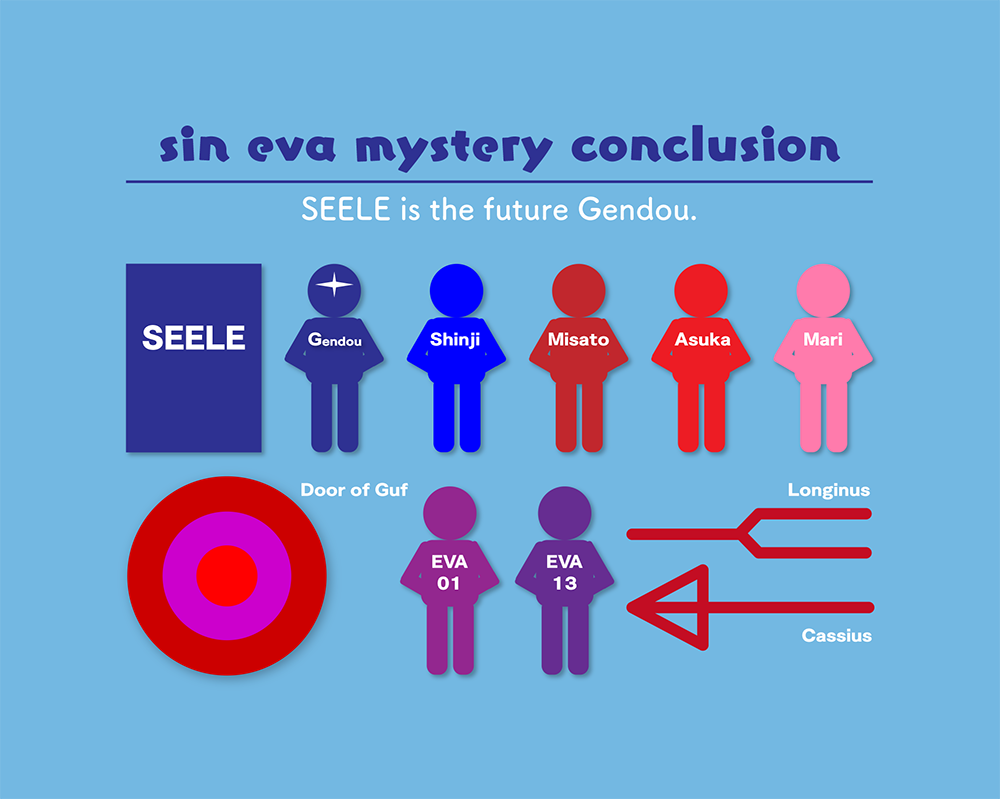

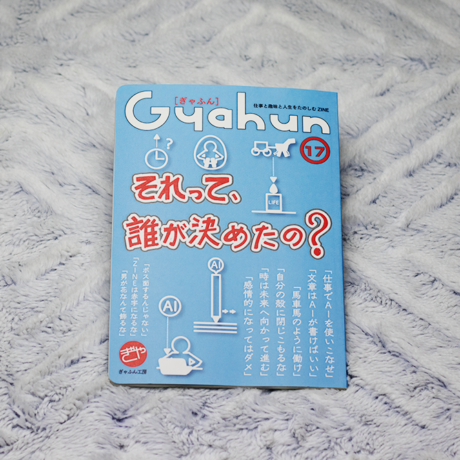
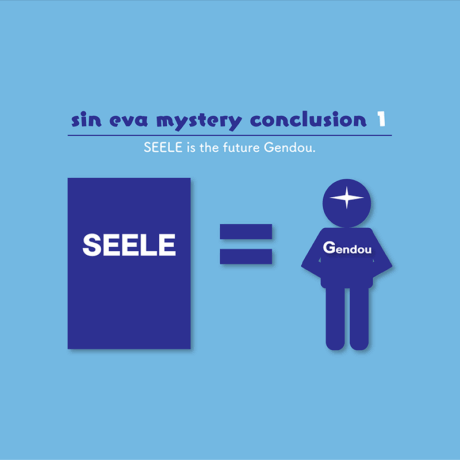
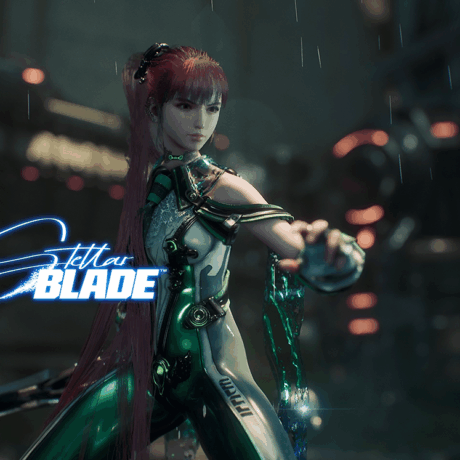
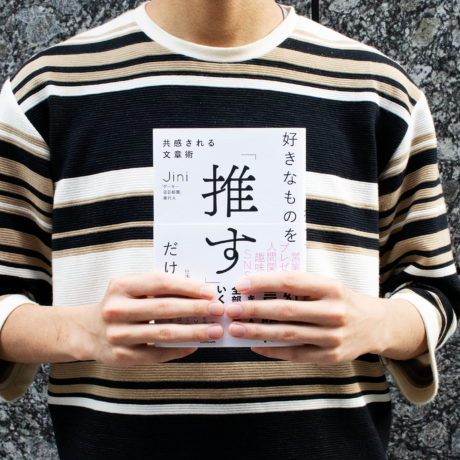
コメント