『かーそる』は、セルフ・パブリッシングの電子雑誌だ。同誌の「創刊にあたって」によれば、
私は常々「知的生産」や「知的生産の技術」について書かれた文章を読みたいと強く望んでいます。しかし、それにぴったりフィットする雑誌は見当たりません。[中略]だったら自分で作るしかありません。
というのが創刊の理由とのこと。
当ブログは、日ごろから「知的生産」について思いをめぐらせるほど人生を前向きに生きちゃいない(そもそもこのブログが「知的」とは縁遠い)。
だが、雑誌として目の前に差し出されたことで、「うむ。自分も『知的生産』の雑誌を読みたかったのかも」と気づかされた。
兎にも角にも、創刊号をダウンロードしてしまったのは事実。そこで今回は、この創刊号を読んで当ブログが考えたことを、とりとめもなく綴ってみることにする。
もくじ
これからのアウトプットは〈知性〉と〈感性〉
この『かーそる』を読んでもっとも目を引いたのは次の一文だった。
こうした営みのコアには「楽しさ」があります。
なぜ、この部分に引っかかったのか?
「知的生産」とは、〈知性〉や〈論理〉あるいは〈理性〉を働かせながら行なう活動であるはずだ。それなのに、「楽しさ」という〈感性〉〈感情〉〈気分〉のようなものが「コア」にある、と述べているからだ。
──そりゃ、おかしいぜ。
と言いたいんじゃあない。じつは以前、とある外資系コンサルティングファームで聞いた話を思い出したのだ。
最新のコンサルティングは“左脳”より“右脳”
「コンサルティング」というと、膨大な資料やデータを収集し、長年培った知識と経験で分析、その結果を資料にしてクライアントに報告する──。門外漢であるわれわれは、そんなイメージを抱く。
しかし、そのようなコンサルティングの手法は、いまや時代遅れだという。
過去のデータからは、予定調和のものしか生み出せない。ユーザーの嗜好が目まぐるしく変わり、市場が激しく変化する現代のビジネス界でそんなことをやっていては取りのこされてしまう。
では、いまビジネスの第一線で活躍するコンサルタントたちは、何をしているのか?
それは、これまでの手法では測ることができない「ユーザー自身も自覚していない感覚的なニーズ」を探りあてる作業だ。
たとえば、旅行会社に対して新しいプランを提案するなら、みずから旅行者となって観光地を訪れ実際に体感してみる。メーカーに対して新しい製品を提案するなら、その製品のモックアップ(試作品)をいちはやく作り、実際にユーザに触ってもらってその感想を聞く。クライアントに対してプレゼンするときは、分厚い資料に書かれた分析結果を長々と説明するのではなく、写真1枚あるいはキャッチフレーズ1つでクライアントの感情に訴えかける。
最新のコンサルティングとは、このようなものであるという。
極端に言えば、いまのコンサルタントが重視するのは〈知性〉や〈論理〉ではない。それらとは対極にある〈感性〉〈感情〉〈気分〉だ。だから、コンサルティングファームでは、従来のようなコンサルタントではなく、デザイナーやプランナーといった異業種の人をどんどん雇いいれているという。
従来のコンサルタントがいわば“左脳型”の人間だとすれば、いまは“右脳型”の人間が必要とされているわけだ。
もちろん、これは直接的には「コンサルティング」、つまりコンサルタントが企業に対して新しいビジネスを提案する場合の話だ。われわれの行なおうとしている「知的生産」とは異なる活動だろう。
たしかに、コンサルタントの相手はクライアントの企業だ。一方で、その企業が相手にするのは一般ユーザーのはず。それは、われわれが「知的生産」を行ない、その成果物を提示する相手とは別だろうか。一致する場合も多いのではないか。だとすると、最新のコンサルティングの手法から学べることもあるはずだ。
つまり、〈左脳〉だけでなく、〈右脳〉を働かせることは、われわれの「知的生産」にも必要なのではないか。
〈右脳〉を働かせる知的生産とは?
では、われわれがふだん行なっているような活動において「〈右脳〉を働かせる」とは、どういうことだろう? 〈感性〉〈感情〉〈気分〉を加味するとは?
ここでは、卑近な例として、当ブログのことを考えてみよう。
当ブログの記事のほとんどが「作品レビュー」だ。書評を載せることもあるが、映画や音楽、ゲームといった感覚的なメディアの作品を扱うことが多い。
レビューの対象は、自分が「おもしろい」と感じたものだ。つまり、感覚的な何か、〈右脳〉でとらえた何かが、記事を書く動機、出発点になっている。
もちろん、〈右脳〉だけでブログは更新できない。実際にレビューを書く段になれば、なぜ「おもしろい」と感じたのか、みずからの感情に向きあい、分析することになる。その作業は〈右脳〉ではなく〈左脳〉の働きによるものと言えるだろう。
また、自分自身の〈感情〉に焦点を当てる一方で、ブログの読者の〈感情〉にも目を向けることが大切かもしれない。自分の記事を読む人はどんな〈感情〉を抱くのか、あるいは抱いてほしいのか。そんな視点が必要になるのだろう。
〈左脳〉だけでなく〈右脳〉も働かせる「知的生産」。その一例として、我田引水的に当ブログを挙げた。もちろん、例としてふさわしいかどうかわからない(先に「知的とは縁遠い」とも書いている)。そもそも「正しい『知的生産』のやりかたはこれだ!」と模範解答を示すように決めつけるのは、創造的な活動になじまない。
「これからの時代、あるべき『知的生産』とは?」。それを探しもとめることそのものが、もしかしたら、これからの「知的生産」なのかもしれない。
〈モノ〉から〈情報〉そして〈カタチ〉へ
さて、このような「〈右脳〉も働かせた知的生産」を何と呼ぶべきか。「呼びかたなんてどうでもいいじゃないか」とも思うが、『かーそる』では、「知的生産」という言葉に疑問を投げかけている。
本来注目すべきポイントとはなんでしょうか。それは「知的生産」という言葉自体が、むしろ「知的生産の技術」の範囲を狭めてしまっている可能性です。
そこで同誌は提案する。
新しい言葉を作るのです。まったく新しい概念を象徴する、まったく新しい言葉を生み出すのです。
これには深く同意できる……というより、おもしろそうだ。それなら当ブログもいっちょ腰を上げようかと思った次第。
梅棹忠夫先生が本家である『知的生産の技術』で示したのは「社会は〈モノの生産〉だけでなく、〈情報の生産・処理・伝達〉にも重きが置かれるようになる」ということだった。つまり、〈モノ〉から〈情報〉へという流れだ。
では、そもそもわれわれは何をしようとしているのか? 「新しい言葉」を見つけるために初心に返ってその問題を考えたい。そして、その答えを得るのに絶好の例があることにすぐに気づいた。そう。この電子雑誌『かーそる』だ。「知的生産」について扱った雑誌そのものが「知的生産」の産物であるとも言える。
ようするに、『かーそる』のようなアウトプットをすることが、これからわれわれが行なうべき「知的生産」だと考えてもよいだろう。
〈モノ〉でも〈情報〉でもないものを生み出す
そうだとして、『かーそる』を制作するような活動を何と呼ぶべきか?
〈モノづくり〉は違う。螺鈿細工の置物とか、漆塗りのお椀とか、工芸品の類を作ることを想像してしまう。〈モノ〉と言うと手で触れるという含みがあり、電子雑誌のようなデジタルデータの制作物を排除してしまう気がする。
〈情報の生産・処理・伝達〉は、さすがに〈モノづくり〉よりは近い。でも、何かが足りない。何が足りないかと言うと、それらはあくまで雑誌制作のプロセスにおいて行なわれることであって、「最終的に成果物として提示する」というニュアンスが含まれていない。それに、「〈右脳〉を働かせて」という意味合いが入っていないのもよろしくない。
いま考え出そうとしている新しい言葉は、「〈右脳〉と〈左脳〉を働かせて何らかの成果物を生み出すこと」。具体的には『かーそる』のようなカタチで読者の前に差し出すことだ。
……ん? 待てよ、カタチ? われわれが生み出そうとしているのは〈カタチ〉、われわれが行なおうとしているのは〈カタチづくり〉なのではないか?
見つけた──。
「〈右脳〉と〈左脳〉を働かせて何らかの成果物を生み出し世に送り出すこと」。これを〈カタチづくり〉と名づけて呼ぶことにしよう。
われわれがこれから行なうのは〈カタチづくり〉
頭を悩ませて捻り出したわりには、普通すぎる言葉という気がしないでもない。だが、よく考えると、我ながら優れた言葉なのではないかと思えてくる。
〈カタチ〉とは、まず視覚や触覚で認識できる具体的な物体である。紙に印刷したものはもちろん含まれる。一方で、紙に印刷していないデジタルデータ、あるいは理論やフレームワークなど、手で触れることのできないアウトプット、抽象的な概念も指ししめすことができる。
さらに〈カタチ〉は、色や音などと同様に〈右脳〉でとらえられるものである。感覚的なものもカバーするわけだ。
そして日本語で「カタチにする」と言うと、何らかの成果物を生み出すことを意味する。それも「労力をかけて」という意味合いを含んでいる。
「カタチづくる」とか「カタチになる」とは言うが、「カタチづくり」「カタチをつくる」とはあまり言わない。「(何かが)カタチづくる」「(何かが)カタチになる」のように、主語は無生物であり自動詞として使うのが基本。「人」を主語とする他動詞として用いることは稀だ(「(人が)カタチにする」は例外的と言える)。だから言葉のアイデンティティーは保たれている。ついでに、「形」ではなく「カタチ」とカタカナにすれば、さらに独自性は高まる。
活動の内容をより正確に表わすなら「〇〇なカタチづくり」「〇〇的カタチづくり」と呼ぶべきかもしれない。でも、言葉は大づかみのほうがいい。いたずらに形容詞をつければ、かえって活動の範囲を制約してしまう。「知的生産」の「知的」がハードルを上げてしまったように。
〈カタチづくり〉。この新しい言葉に共感は得られないかもしれない。でも、それでいい。当ブログだけで通用する用語であっても、いっこうに気にしない。これからガシガシ使っていくことにしよう。
『かーそる』とは良い名前をつけたもんだ
ところで、同誌には「かーそる」の意味についてこう書かれている。
カーソル(cursor)は、「現在の入力位置」を示します。つまり、「かーそる」というタイトルは、私たちの「今」を示すものだとも言えますし、風呂敷を広げていいならば、「この雑誌こそが最前線なんだ」という意思表示でもあるわけです。
なるほど。じつに良いネーミングだ。「やられた」という感じがする。
「カーソル」は、毎日のようにお世話になっているものだ。われわれの作業に欠かすことができない。それでいて、ふだんはその存在と重要性について意識することはない。いちいち意識していては作業の妨げになる。さらに、「カーソル」とひとくちに言っても、さまざまな〈カタチ〉がある、というのも付けくわえよう。
これらの特徴は、まさに「知的生産」、いや〈カタチづくり〉もまったく同じ。これほど的確な名前はほかにない、と感心させられた。
次号では「かーそる」でいったいどこを“クリック”するのか、じつに楽しみだ。
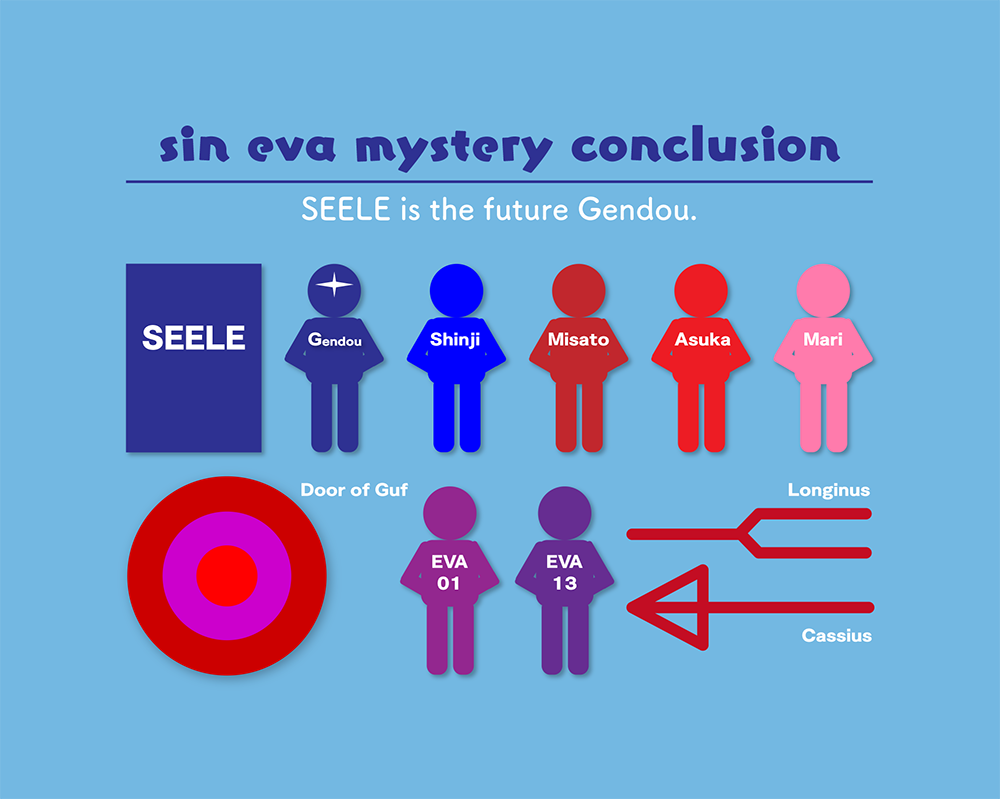

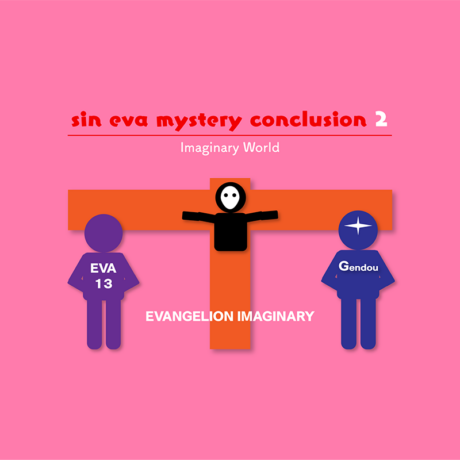
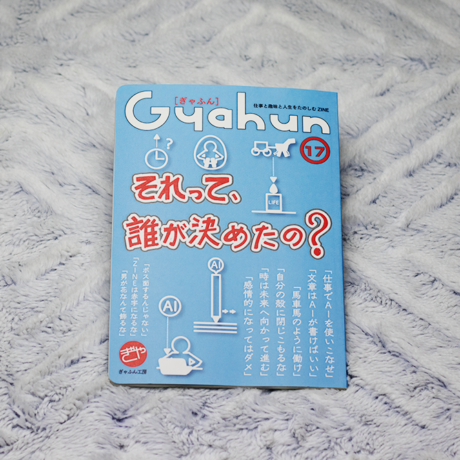
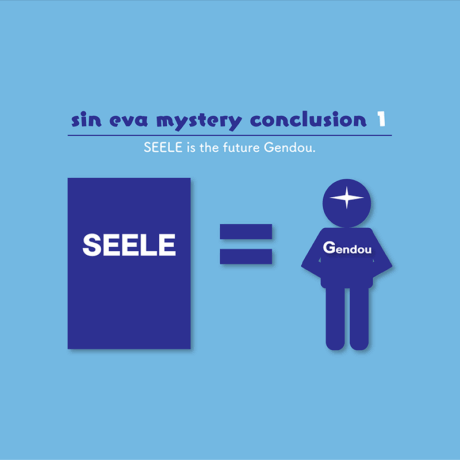


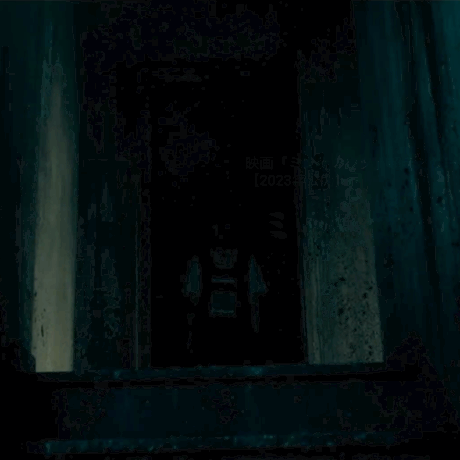
コメント