大量虐殺を誘発するという謎の“器官”。その鍵を握る人物を追って、アメリカ軍大尉が紛争地帯へ飛ぶ。伊藤計劃『虐殺器官』はそんな物語だ。
今回は夭折した著者の話題作をレビュー。
【レビュー1】虚構と現実の狭間を行き来するSF的描写
物語世界では、“戦争”をより合理的に、言葉を変えれば、兵士たちをより“道具”に近いものにするためのテクノロジーが使われている。
この描写がおもしろい。
ただし、そのテクノロジーは、兵士個人はもちろん、人々を、社会を幸福にするために開発されているわけではない。そこに哀しみが漂う。
SFならではの描写に心躍らせつつも、物語世界に住む人々へ憐れみを覚える。
その相反する感情を呼び起こしてくれる不思議な作品だ。
【レビュー2】戦争を描く残酷描写
戦地は死屍累々だ。子ども、女、老人……。そこでは、弱いものから骸になる。ただの物質と化す。はらわたをさらしながら横たわる。
戦争というものの残虐さを、乾いた筆致で描き出していく。その描写を“悪趣味”と非難するには、あまりに淡々としすぎている。
だから、むしろ生々しさは払拭され、残酷な世界だけが浮き出されていく。
【レビュー3】じつは語っているのは「私とは何か」という哲学
この作品から何を感じるかは人それぞれだ。個人的には、上記のSF描写、残虐描写は飾りにすぎないと考える。
物語で語られるのは、自我とは何か、自分とは誰か、考えるとは何かという哲学的考察だ。
魂がある、肉体を離れた人間の崇高な中枢がある、と考えたほうが、ぼくが見殺しにしてきた多くの子供たちや、手にかけてきた多くの独裁者やごろつき、そうしたものの命を奪ったという罪を軽減できる──そうした魂がしかるべき生を営むことのできる、天国とか地獄とかいうオルタナティヴな世界を想定すれば。
現実世界で起こる戦争やテロ、殺人などといた、目を覆うばかりの現状に対し、われわれは語るべき「言葉」を持たない。
罪や罰、社会といった概念で説明できた気になる。いや、自分を納得させる。
そんな思考過程の原点。読み進めるうちに「考えるとは」「私とは何か」という原始的思考にまで遡らされてしまう。
左右問わず極端な政治思想が虐殺を引き起こすのではなく、むしろ虐殺を準備するディテールとして右だの左だのといった政治思想が要請されるのではないか、とね。
だから、じつはこの作品は「SF小説」でも「戦争小説」でもなく「哲学の書」なのだ。
SF・戦争モノとして読むと楽しめないかも
……というのは、まさに自分がそう思いながら読んでしまったからなのだ。
SF描写はテレビゲームの『メタルギアソリッド』に似ている。伊藤氏にはそのノベライズもあるので、目新しさはない。
戦争モノとしても、アクションのカタルシスを期待すると肩透かしで終わってしまうだろう。
最初から作者の意図が“哲学”なのだから、これらは欠点ではないとしても、誤った期待をしてしまうと、時間を浪費することになってしまう。そこだけが注意点だ。
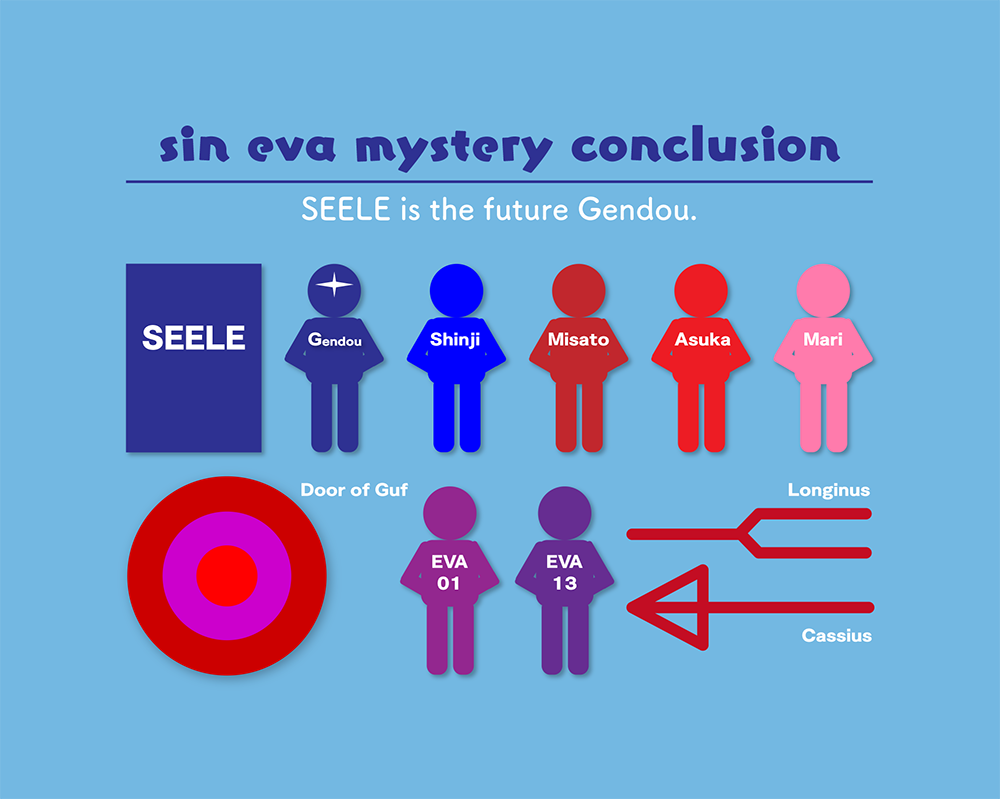


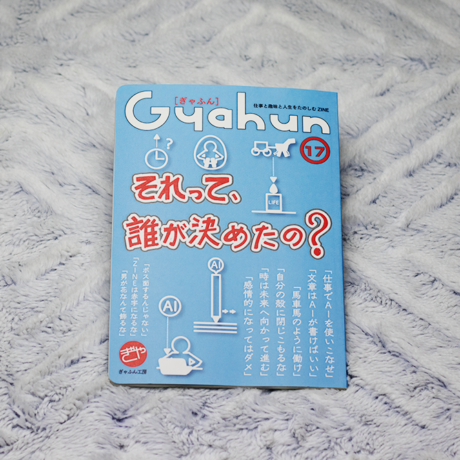
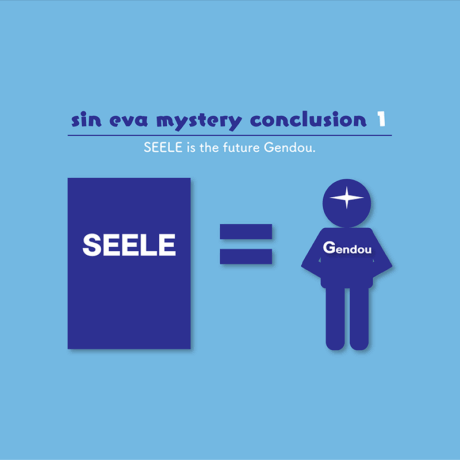


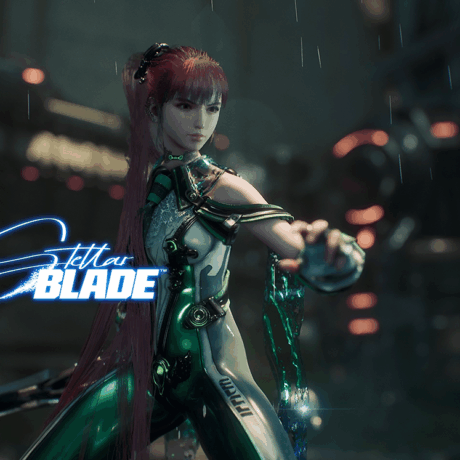
コメント