昭和64年に起きた誘拐殺人事件を巡る警察内部の抗争を描く、横山秀夫『64(ロクヨン)』。
“横山作品にハズレなし”と常々感じていたが、本作はそれをまたしても証明した。
[ハズレなし]1.地味な設定ながらダイナミズムがある
警察モノの名手である横山秀夫。本作も警察組織を舞台にしているだけあって、その手腕は振るっている。
今作の主人公は、刑事ではなく、警察の広報マンだ。事件を直に追うわけではないので、言ってみれば地味な描写になる。
しかしながら、そこには確かなドラマがあり、ダイナミズムがある。物語の次の展開を期待させるサスペンスにあふれている。
いわば「事件は会議室で起きている」わけだ。
そして、ほんとうに「会議室」だけで物語が終始するわけではない。きちんと警察モノとして「事件発生→捜査→解決」のカタルシスが得られるようになっている。
[ハズレなし]2.事件報道は匿名か実名かと唸らせる
今作で物語の中核をなすのは、マスメディアとの攻防だ。具体的には「事件の当事者を実名で報道するか、匿名とするか」がモチーフとなる。
「だから新聞に名前を出して断罪するってわけか」
「あ、そういう言い方はないでしょう! そんな話をしてるんじゃありません。警察が勝手に判断して名前や住所を隠すのがおかしいって言ってるんですよ。実名で書くか書かないか、それは我々が公益性に照らして判断することです」
実名・匿名報道は、古くて新しい問題だ。最近でも話題になった。事あるごとに問題が持ち上がるが、一向に解決はみない。
「記者と完全に決裂してしまえば、ウチは宣伝の媒体をみすみすドブに捨てることになります。かといって、彼らの要求を丸呑みしていたのでは捜査機関たる警察が普通の役所に成り下がってしまう。それに最近は人権だのプライバシー保護だの色々うるさいですからね、すべてのケースを実名で発表すれば、文句を言う当事者が増えてウチに対する世論の風当たりがきつくなる。詰まるところ、匿名問題は『話し合いは平行線のまま、しかし継続している』という状態を維持していくほか当面方策がありません。戦果は得られずとも、警察の広報を攻撃している限り、記者の面子だってぎりぎり立ちますから」
警察の言い分。報道する側の論理。どちらにも理はある。しかし、この問題において忘れてはならないのは、あくまで被害者・加害者を含めた「我々」の利益だ。だからこそ、警察、報道陣、両方の理屈を検討する必要がある。そして、本作ではそれが克明にリアリティをもって描かれる。
匿名の壁の向こうでは、どれほど奇天烈な作り話も命を得られる。大手を振って歩ける。どんな展開も許される。物語を紡ぐうえで匿名は万能の神であり、無限の選択肢を許容する構造は妄想そのものなのだ。
この問題を誰もが自分のものにするために、本作は有益な参考書にもなりうるだろう。
[ハズレなし]3.働く男の矜持を突きつける
刑事はどのようなメンタリティで事件を追っているのか。
愚痴らず楽しめ。俺たちは給料を貰って狩りをしてるんだからな──。
理性はともかく、犯罪を憎む本能は刑事に備わっていない。あるのはホシを狩る本能だけだ。
本作で描かれている刑事の本心が、実際そのとおりであるかは知らない。でも、いかにもありそうだという現実味は持っている。それに、真実かどうかは問題ではない。
それらは、刑事だけでなく、仕事に賭ける男に共通する心情なのではないか。そう思わせるところに、本作の魅力がある。
本心から従順な部下など存在しないし、部下の内面を掌握している上司もまた存在しないと知っている。なのに自分だけは神になる。部下がつくたび使い勝手を考え、こいつはこんな部下、あんな部下と分類し、自分にとって便利でわかりやすい単色のラベルをせっせと貼ってきた。
「働く男の矜持」。いささか時代錯誤な表現かもしれない。しかし、警察はまさに旧態依然とした組織だ。いわば男尊女卑の思想がしっくりくる。
では、警察で働いているわけでもない我々が、現実世界で本作のようなプライドを持つことは適切か。
そこまで敷延することは、無理かもしれない。サラリーマンのような人間は本作に登場しないし、自分の姿を劇中の人物に投影するのは難しい。
それでも、自分を見つめ直したい。仕事に忙殺される日々の中、少し立ち止まりたい。そんな時には、本作の主人公の心情に想いをはせることは有益だ。
長編をここまで一気に読ませる手腕に感服
自分自身も小説を制作している者のひとりとして注目すべき点がある。
とにかく文章にキレがある。
プロの作家、それもベストセラー作家だから当たり前かもしれないが、「キレ」は必ずしもプロの作家の条件ではない。
個人的にはKindle版(電子書籍)を読んだが、紙の本では647ページの大長編。それを一気に読ませるのは、この文体があってこそだ。
自称・小説家として大いに参考にさせてもらった。
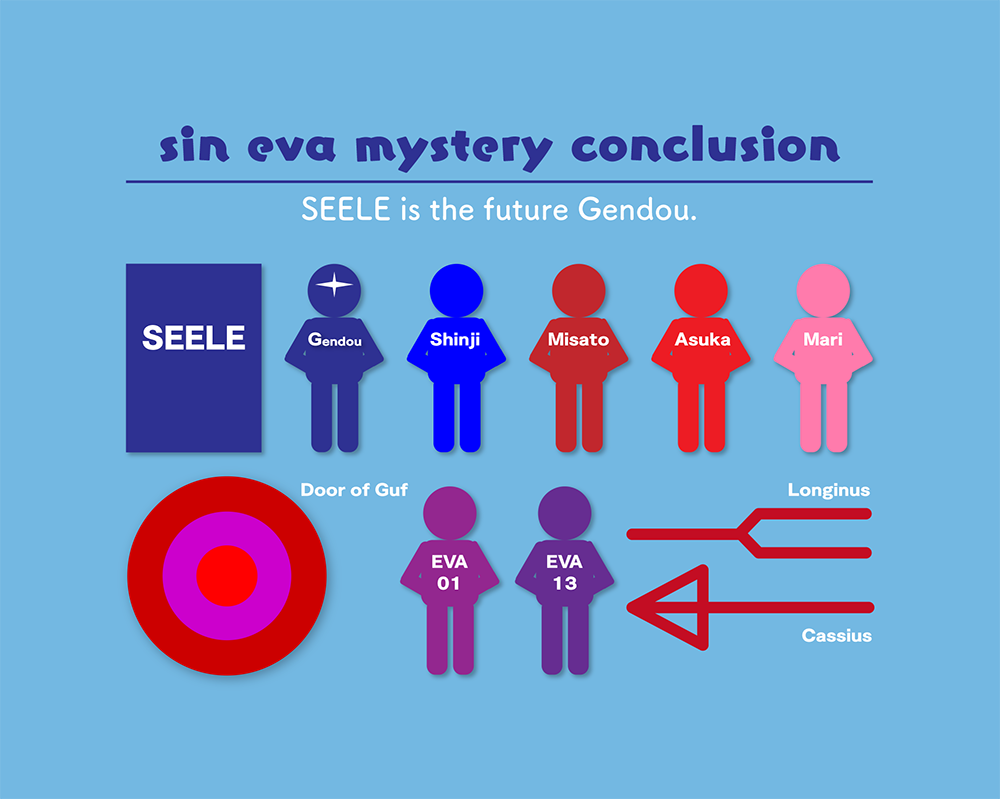


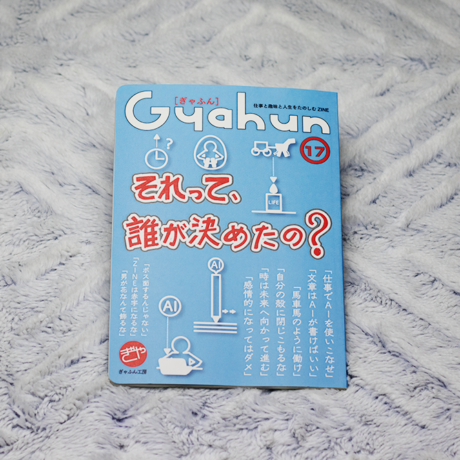
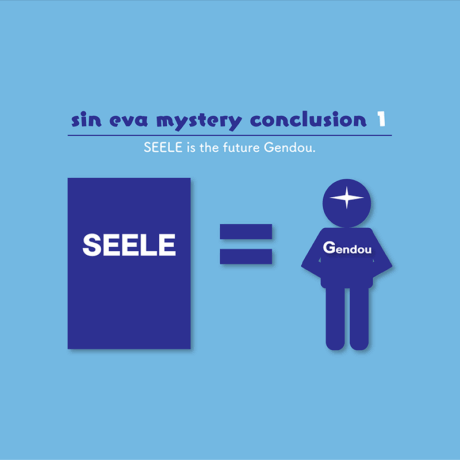
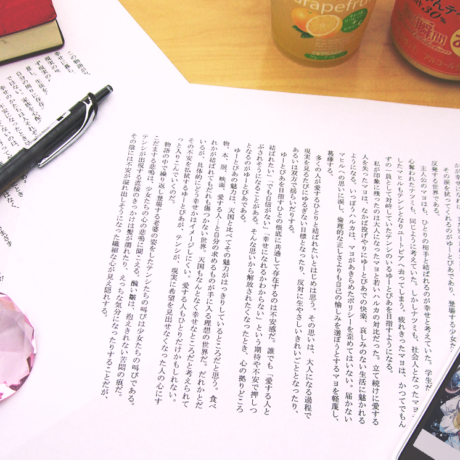
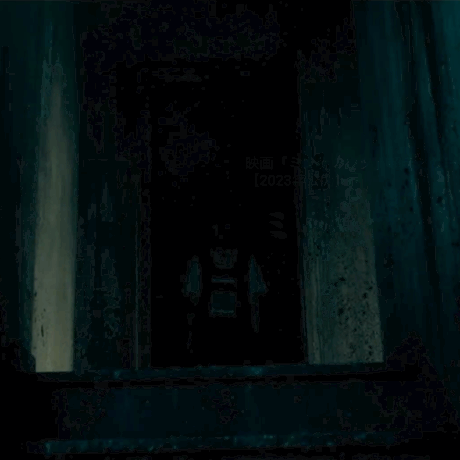

コメント