じつは〈透明人間〉の物語は怖くない。でも本作『透明人間』は、紛うことなき「ホラー映画」だ。しかも傑作のそれ。今回はだから、本作をホラー映画たらしめている“何か”を探りあてることによって、面白さの秘密に迫ってみたい。
[基本的にネタバレなし。鑑賞前の判断材料としてご利用ください]
ホラー映画のモンスターは超自然主義的である
本作『透明人間』のタイトルにもなっている〈透明人間〉という題材についてあらためて思いをめぐらすと、とても興味深い真実に行きつく。それは
〈透明人間〉はホラー映画になりえない
ということだ。
それはなぜか?
ホラー映画に出てくるモンスター・異形(すなわち劇中の人物や鑑賞者が「ホラー」の感情を催す対象)は、基本的にふつうの人が持つ規範や科学的常識・倫理観・価値観・世界観から逸脱するものでなければならない。つまり、わたしたち鑑賞者(および劇中の人物)は、この「逸脱」に恐怖をおぼえることになる。
たとえば、悪魔や死霊・エイリアンの類いは、劇中の世界観において「ありえない」モノであり、それゆえに鑑賞者および劇中人物は恐怖するわけだ。
ただ、こと〈透明人間〉に着目した場合、〈透明〉とはいえ〈人間〉ではあるので、劇中の社会通念としても、また科学的観点から見ても、けっして「逸脱」したモノではない。言い換えると、『透明人間』というタイトルがつけられる物語において、〈透明人間〉はありえないモノではなく、なんらかの自然主義的な(超自然主義的でない)説明がつけられるということだ。
その証拠に、〈透明人間〉が登場する物語では一般的に劇中で「なぜ透明なのか」を説明する描写があり、鑑賞者および劇中人物が合理的に納得できるようになっている。この点は本作も例外ではない。
「合理的に納得できる」のであれば、それが「ホラーの感情」を与えることはない。ズバリ怖くない。だから、順当に考えれば、〈透明人間〉が登場する物語は、ホラー作品にはなりえないのだ。
もちろん、恐怖を催すモノが超自然主義的である、という決まりがすべてのホラー作品を網羅するものではない。例外はいくらでも挙げられる。ただ、この決まりにしたがっていないにもかかわらず、ホラー作品たりえているならば、その理由を精査・検討する必要があるだろう。
本作『透明人間』をホラー作品たらしめている“何か”。次にそれを探っていこう。
典型的なホラー映画のプロットにしたがっている
「ホラーを与えるモノは超自然主義的である」。これをホラー映画の第一法則とでも呼ぶとするならば、第二法則は
ホラー映画の典型的プロット・パターンにしたがう
と指摘できるだろう。
ホラー映画の物語はおおよそ次のように展開していく。
- 登場
- 発見
- 確証
- 対決
典型的なホラー映画の展開はこうだ。物語の序盤でモンスターが「登場」し、劇中の人物(おもに主人公)によって「発見」される。だが、モンスターは超自然主義的であるために、主人公以外はその存在を信じることができない。そこで、主人公はモンスターの存在を人々(協力者や警察・軍隊など)に「確証」させるべく奮闘する。これが中盤の展開となり、終盤では主人公はモンスターとの「対決」へと進んでいく。
怪物や悪魔・心霊・殺人鬼が出てくるホラー映画は、ほとんどの場合、このプロット・パターンにしたがっているはずだ。その点をあなたも確認していただきたい。
もちろん、やはりこのプロット・パターンがすべてのホラー映画を網羅しているわけではない。「登場」の描写がなかったり、「対決」しないまま物語が終わったりすることもある。プロットのカタチには大小さまざまなバリエーションが考えられる。
しかし、本作『透明人間』には、(ややネタバレになるが)この典型的なプロットがピタリとあてはまる。
つまり、〈透明人間〉という題材ではホラー作品にはなりえないが、典型的なプロットを採用しているために、ホラー映画として成立させることに本作は成功しているのだ。
本作の制作陣はホラー映画のつくりかたを熟知した手練れである、と高評価に値しよう。
とはいうものの、ホラーのプロット・パターンにしたがえば、ただちにホラー映画がつくれるわけではない。少なくとも傑作にはならない。本作にはまだまだ面白さの真髄が隠されているようだ。
フィルムに映らないモノをフィルム上で表現した
本作の面白さの真髄に迫るために、〈透明人間〉そのものにあらためて焦点を当ててみよう。すると、興味深い点に気がつく。それは、
〈透明人間〉はフィルムに映らない
ということだ。映画においてフィルムに映らないモノは存在しないのとおなじだ。この映画の“宿命”は本作『透明人間』の制作陣の頭を悩ませたのではないかと想像する。フィルムに映らないものをどうやって表現すればいいのか、と。
そこで制作陣は、存在しないものを「存在」しているように見せることに腐心した——のではなく、存在/不存在という問題そのものをホラー(恐怖)の対象にして物語を構築した。
〈透明人間〉を「存在/不存在」の境界にいるモノとして設定すれば、「ありえる/ありえない」の揺らぎ、「逸脱している/していない」の間を行き来するモノとして表現できる。「自然主義的/超自然主義的」の両方の性質を持つ“モンスター”として登場させることができるわけだ。
そこに本作の面白さの真髄がある。
本作『透明人間』を鑑賞しはじめたとき、わたしは「心霊ホラーの映画を観ているようだ」と感じた。髪が長く白い着物を着た女の幽霊が恨みを抱き、人々に呪いをかけていく映画を観ているときのような嫌悪感や忌避感・緊張感をおぼえたのだ(心霊モノではたいていの場合、呪いをかけた張本人は最後のクライマックスまで姿を見せない——つまりフィルムに映らない)。
この感覚は制作陣が鑑賞者に対して確信的に催させているものだ。つまり、計算どおり。
というのは、幽霊こそ超自然主義的なモノの典型例だからだ。科学的な常識を持ち合わせているわたしたちは、幽霊など存在しないと理解している。存在しないはずモノが存在している(ように描かれる)からそこにホラー(恐怖)が生まれる。
本作の真髄とは、端的にいえば、〈透明人間〉を“幽霊”として表現した点にあるといえるだろう。
今回の論旨をまとめてみよう。
ホラー映画のモンスターは超自然主義的でなければならないが、〈透明人間〉は自然主義的である(劇中で「透明」である理由が合理的に説明される)。したがって、ホラー映画になりえない。
しかしながら、本作はプロット・パターンに忠実にしたがうことで、ホラー映画として成立させている。
また、〈透明人間〉はフィルムに映らないため存在しないことになるが、制作陣は「存在/不存在」の揺らぎを逆手にとって、本来は自然主義的であるはずの〈透明人間〉を超自然主義的に表現している。つまり、本来〈透明人間〉はホラー映画のモンスターになりえないはずだが、制作陣はそれを実現している。
そこに本作の卓越性と真髄がある。
[参考文献]ノエル・キャロル:著/高田敦史:翻訳『ホラーの哲学 フィクションと感情をめぐるパラドックス』(フィルムアート社)
©2020 Universal Pictures.
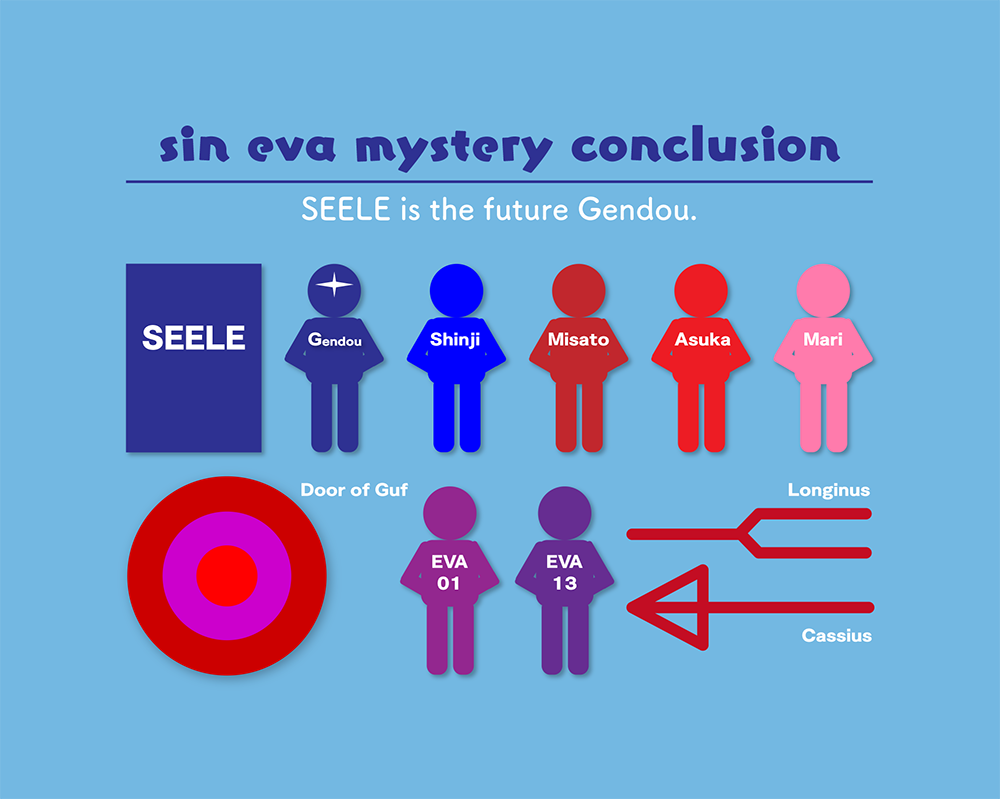

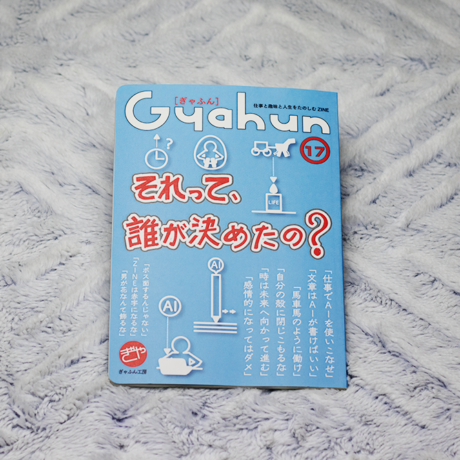
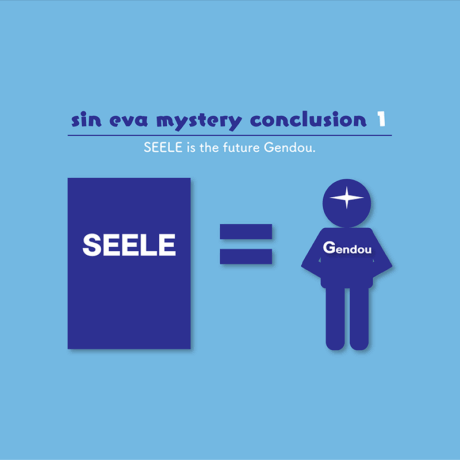
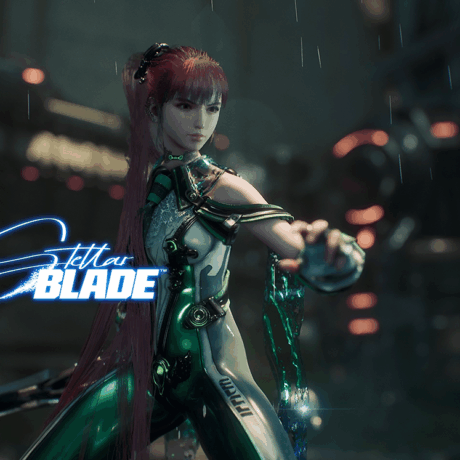

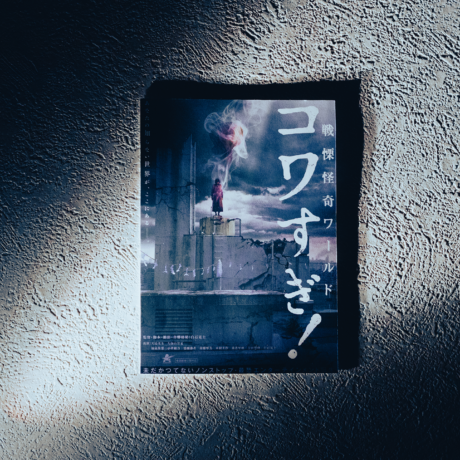
コメント