『呪怨:呪いの家』について語るとき、下のスクリーンショットがよく使われる。

あなたはこれを見て「本作は自分のために創られた作品だ」と思い、すかさずNetflixにアクセスしたのではないだろうか。当ブログもそんなホラー好きのひとり。
この画像は、たしかに本作を象徴するシーンだ。すべてのエピソードを観おわったいまも強く印象に残っている。けれども、しょせんは視聴者を誘いこむための“撒き餌”。本作から得られる〈恐怖〉の本質を表わしてはいない。
いや、コトバを変えよう。本来の〈呪怨〉が持っていた“2つの恐怖”のうち、片方しか表現していないのだ。
本作が持つ真の〈恐怖〉は、“もうひとつ”のほうにある。
もくじ
〈呪怨〉が持っていた“2つの恐怖”

〈呪怨〉の恐怖表現はそれまでの伝統を覆した
かつて〈呪怨〉の持っていた“2つの恐怖”とはなにか?
ひとつは、「それまでのジャパニーズ・ホラーの伝統を覆す画期的な表現による恐怖」だ。
〈呪怨〉以前に創られた日本のホラー映画において、“あの世のモノとおぼしき存在”は、画面の端にチラリと映りこんだり、微妙に声が聞こえたりと、その存在を誇示することはなかった。だからこそジワジワと忍びよる〈恐怖〉が味わえた。
ところが、〈呪怨〉はその定型をあえて崩した。異形は正々堂々と画面に映りつづける。それも長時間にわたって。ガッツリと照明もあたる。存在感は圧倒的だ。それでいて、しっかりと怖がらせてくれた。
また、「呪い殺す」のは、まさに“この世ならざるモノ”の伝統的なお家芸。〈呪怨〉までの作品では、劇中でそれとなく結末をほのめかす程度で、実際に「殺される」場面は描かれなかった。だからこそ“余白”を想像する余地が生まれ、〈恐怖〉が増幅した。
しかしながら、〈呪怨〉ではバケモノが人に“攻撃”を加える様をまざまざと描写する。あるいは、人が変わりはてた姿をあからさまに表現する。その様子に観る者は戦慄した。
さらに、トリッキーな恐怖表現も〈呪怨〉の十八番だ。時系列が前後して事件が起こったり、無関係だと思われた人物たちがのちに関連づけられたり。あたかもバケモノが時空を操る超能力を持っているかのようなふるまいを見せた。そこに新たな〈恐怖〉が生まれたのだ。
これらを「〈呪怨〉らしさ」と考えるなら、本作『呪怨:呪いの家』でもほぼ再現されている。かつて〈呪怨〉の恐怖を味わった者は、本作も十分に満喫できるだろう。もちろん、〈呪怨〉をよく知らない人も独特の演出に舌を巻くはずだ。
冒頭に掲げた画像は、まさに〈呪怨〉の革新的な恐怖表現(を再現したもの)を象徴する一枚といえる。
〈呪怨〉は“いまそこにある恐怖”をもたらした
〈呪怨〉が楔を打ちこんだ「画期的な表現」も、“恐怖のインフレーション”を起こせば怖くなくなっていく。「画期的」なことを長年くりかえしていれば、それは〈革新〉ではなく〈保守〉になってしまう。近年の〈呪怨〉がいまいちパッとしなかったのもそこに原因がある。
本作『呪怨:呪いの家』の制作陣は、〈呪怨〉の持っていた“2つの恐怖”のうち、いままでだれもが忘れかけていた“もうひとつの恐怖”に着目した。
“呪怨のもうひとつの恐怖”とはなにか?
当初の〈呪怨〉は「心霊実話モノ」をコンセプトとしていた。つまり「それがあたかも実話であるかのような語り口」だ。最近の〈呪怨〉はこれがなおざりになっていた。
初期の〈呪怨〉はフィルムカメラではなく、ビデオカメラで撮影されていた。そうすることで“虚構性”が薄まり、“日常と隣りあわせにある恐怖”をもたらした。「じつはこんなことが近所の家で起こっているのかも」「自分に似たような災難がふりかかっても不思議ではない」などといった、ほどよいリアリティを味わうことができた。
じつをいうと「それがあたかも実話であるかのような語り口」は「だれもが忘れかけていた」わけではない。投稿映像にもとづくフェイクドキュメンタリーシリーズでは、“日常と隣りあわせにある恐怖”を体感でき、現在も発展をつづけている。
これらの作品では、市井の人々がビデオカメラやスマホのカメラで撮った映像に、奇妙なモノが映りこむ。なにげない日常のなかに異界のモノが闖入する。そんな〈恐怖〉をもたらす。
現在、もっとも〈恐怖〉を味わえるホラーはこの「投稿映像にもとづくフェイクドキュメンタリーシリーズ」であると、当ブログは断言する。
ただし、本作『呪怨:呪いの家』が登場するまでは。
日常の世界で〈因果律〉が成立しない恐怖

本作にしかけられた“日常と隣りあわせにある恐怖”
本作『呪怨:呪いの家』は、「フェイクドキュメンタリー」ではない。紛れもないフィクションとして創られている。「ドキュメンタリー」の体裁をとっていない。
では、本作ではどのように〈呪怨〉の“もうひとつの恐怖”、すなわち“日常と隣りあわせにある恐怖”を表現しているのだろうか。
ポイントは、本作の舞台が1980年代後半から1990年代の日本に設定されている点にある。これこそが本作にしかけられた最大の“トリック”だと当ブログは考えている。
1980年代後半から1990年代の日本はどんな時代だったか? と問われて、あなたはすぐに答えられるだろうか? そもそも生まれていなかったかもしれない。
しかし、当時のことを思い出したり調べたりする必要はない。「どんな時代だったか」は、劇中で表現されているからだ。
甚大な被害をもたらした大災害、陰惨なテロ事件、目を覆いたくなる殺人事件が頻発した。当時の日本は、その意味で“恐怖”の時代だったといえる。
本作では、当時の災害や事件がおもにニュースの映像として画面に映る。現実で起きた出来事が虚構に入りこんでいる。本作を観ているうちに、かつての〈恐怖〉が心のなかから引きずり出されてしまうのだ。
これが本作の“日常と隣りあわせにある恐怖”というわけだ。
そこに本作の〈恐怖〉の本質が潜んでいる。
ただし、これだけでは〈恐怖〉の半分しか解明できていない。
本作が実際に起こった出来事を取りこんでいるのは、“現実味”を持たせる以外に、もうひとつ意図があると思われるのだ。
じつは「呪いの家」はたいして怖くない
〈呪怨〉の物語をひとことで説明すると、「呪われた家に入った者が次々と呪われてしまう」話だ。本作『呪怨:呪いの家』もタイトルが示すとおり、その設定を踏襲している。
なにも悪いことをしていないのに、家に入っただけで呪われてしまうのは、相当な〈恐怖〉といえる。自分が登場人物のような災厄に見舞われたことを想像すると震えがくる。この理不尽さこそ〈呪怨〉が表わす〈恐怖〉の本質であり、本作にもしっかりと受けつがれている。
ところが——。
本作が表現する〈恐怖〉の本質の向こう側に〈真髄〉ともいうべきものが隠されている。あなたは本作を観おわったあと、なんともいえない後味の悪さに苛まれたはず。それは、無意識のうちに本作の〈真髄〉がココロのなかに巣くってしまっているからなのだ。
では、本作の〈真髄〉とはなにか?
「呪われた家に入った者が次々と呪われてしまう」のは、そこに決まりごと・法則・ルールが存在していることを意味する。「原因があるから結果がある」という〈因果律〉が成立するわけだ。
ということは、裏を返すなら「呪われた家に入らなければ呪われない」ことになる。そう考えると(いささか興ざめだが)「呪いの家」なんてたいして怖くない(そもそも「呪いの家に入らなかった者」が主人公になるはずがないので、そんなことは観ている者の意識にはのぼらないが)。
しかしながら——。
本作では呪いの家に入らなくても呪われてしまうのだ。
もしも、あなたがすでに本作を観ていたとしたら、ここで異議を唱えたくなるはずだ。そんな場面は本作にないぞ、と。
もう少し説明させてほしい。
人知のおよばぬ〈因果律〉が成立してしまう恐怖

「呪い」より恐ろしい〈恐怖〉が忍びよる
たしかに、本作も「呪われた家に入った者が次々と呪われてしまう」。そんなストーリーだ。だが、なぜ彼ら・彼女らはそもそも「呪われた家」に足を踏みいれたのか? 偶然? そうかもしれない。たまたま怪異に遭遇した者たちの行く末を物語にしている(なにも起こらなかったらドラマにならない)。たしかにそのとおり。
しかし、本作には「偶然」のひとことでは片づけられない真実が存在する。
どういうことか? ここで本作にしかけられた“トリック”が生きてくる。
1980年代後半から1990年代の日本で起こり、観る者のココロのなかに燻りつづける災害や事件。これらが本作のなかでも(画面外で)起こっていることが示されるのは、すでに述べたとおり。
では、これらの災害や事件に〈因果律〉は見出せるだろうか? 災害の起こるしくみや加害者の動機などに迫ることで、小さな「原因と結果」のようなものは見つかるかもしれない。しかし、「それが起きたのは、なぜそのときだったのか」「犠牲になったのは、どうしてその人たちだったのか」などについては、「○○だから」といった明確な〈因果律〉を示すことはできない。
人はそれを「不幸」とか「不運」「不条理」などと呼ぶだろう。〈因果律〉が見出せないときに、とりあえず“理解”したつもりになるためのレッテルだ。
災害や事件に〈因果律〉が存在しないなら、本作の登場人物たちが被る災厄にもまた〈因果律〉を見出せない。
ここで当ブログは、めまいがするほどの〈恐怖〉を覚える。
なぜなら——。
「呪い」によって人生がねじ曲がっているのなら、「呪い」を解けば問題は解決するはず。ふつうはそう考える。実際、本作の登場人物も「呪い」の謎を求めて奮闘する。
ところが——。
本作の「呪い」に〈因果律〉は存在しない。だから、解くことはできない。そもそも「呪いの家に入ったから呪われた」とはかぎらない。なぜなら「原因があるから結果がある」という〈因果律〉が働いているわけではないから。そんな仮説も立てられてしまう。そうすると、(タイトルにうたっているにもかかわらず)本作で起きている怪異は「呪い」ではない、と考えることすらできる。
理由がないのに災難がふりかかる。となれば、われわれが住む現実世界において、いつ・どこに、おなじような怪異が訪れても不思議ではない。なぜなら端から〈因果律〉が成立していないのだから。
そんな恐るべき真実が浮かびあがってくる。
本作が実在の事件をあえて描写しているのは、「この世で起こる出来事に〈因果律〉は存在しない」ことを示すためだと考えられるのだ。
「呪い」が“自然現象”になる戦慄の真実
そして、本作『呪怨:呪いの家』の〈真髄〉は、ここから先にある。
1980年代後半から1990年代に起こった出来事、および本作で描かれる「呪い」に〈因果律〉は存在しない。ただし、それはわれわれ人間が認識できる範囲において、だ。
どういうことか?
災害や事件、「呪い」は、特別なこと、めったに起こらないこと。われわれはそう考えている。しかし、その認識は正しいだろうか? その疑問が拭えない。
ほかのことにたとえてみる。月の満ち欠け、台風や雷、樹木の紅葉。それらの存在を知らず初めて目にした人は、「特別なこと」「めったに起こらないこと」だと思うのではないだろうか。だが、われわれはそれらが「特別」ではないことを知っている。
月の満ち欠けなどの自然現象がどうして起こるのか。その〈因果律〉は科学的に解明されている。だからこそ「特別」とは考えない。当たり前のこととして受け入れている。
その一方で、前述のとおり、災害や事件、「呪い」に〈因果律〉を見出すことはできない。しかしながら、もしかするとわれわれの知覚できないところで〈因果律〉が働いているかもしれない。そんな想像も成り立つ。
人によっては、その〈因果律〉を“神の御心”とか“偉大なる創造主の意思”とか“宇宙の絶対法則”などと呼ぶかもしれない。人知のおよばないシロモノだから、なんと表現しようとまちがいではない。
災害や事件、「呪い」でさえも、人知のおよばぬ“視点”で眺めれば、月の満ち欠けや樹木の紅葉とおなじような“自然現象”なのかもしれない。そうすると「呪い」が、紅葉とおなじ程度のたしからしさで、われわれの世界で起こりうることになる——いや、まさにいま現実世界で起こっているのかもしれないのだ。
本作の登場人物たちが「呪いの家」に吸い寄せられ人生が崩壊していったのは、“神の御心”や“偉大なる創造主の意思”あるいは“宇宙の絶対法則”によるもの。そもそも、「呪い」をかけている張本人とおぼしい「白い服の女」でさえも、“人知のおよばぬモノ”に導かれたにちがいない。そして、それはけっして「特別なこと」ではなく“自然現象”なのだ。そんな戦慄すべき真実が見えてくる。
“神の御心”や“偉大なる創造主の意思”あるいは“宇宙の絶対法則”に、われわれ人間のようなちっぽけな存在が抗うことなどできるはずがない。「呪い」を解こうとしてもムダ。なにも変わらない。どうあがいても絶望。そんな悟りの境地にたどりつく。
「呪われた家に入った者が次々と呪われてしまう」。いまとなってはありきたりの物語を表で展開しながら、裏では「じつは呪いさえも自然現象である」という“世界観”を本作は提示している。
本作が持つ〈恐怖〉の真髄はそこにある。
これを書いているいまも、震えは止まらない。
©2020 NBCUniversal Entertainment All Rights Reserved
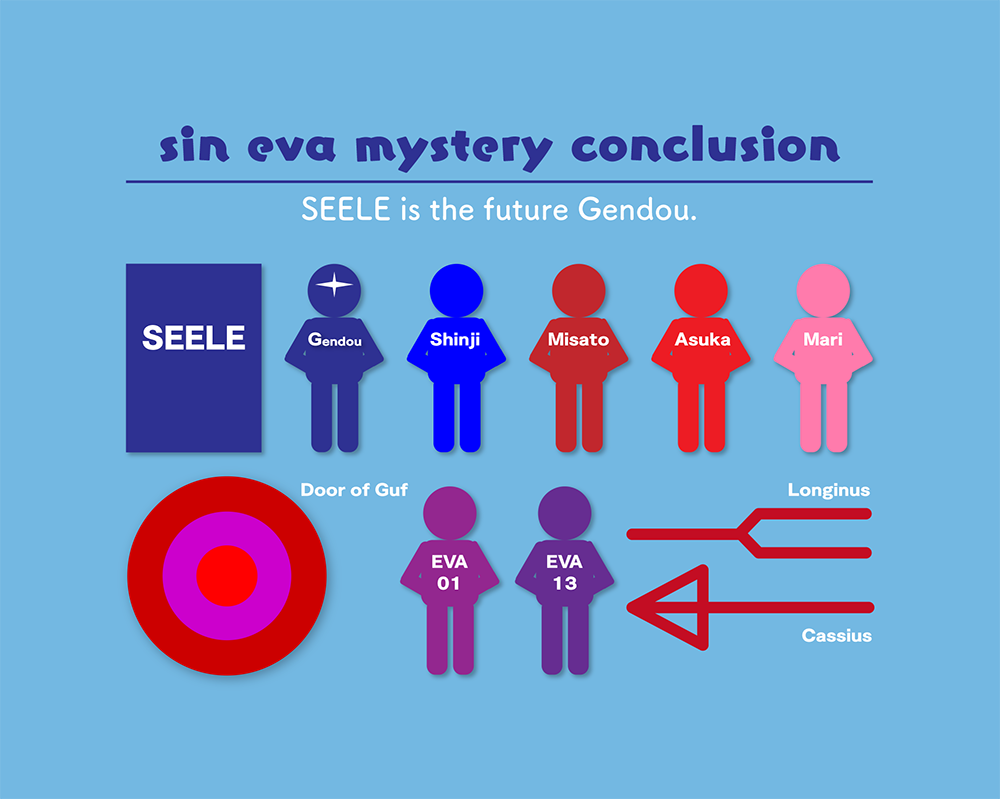


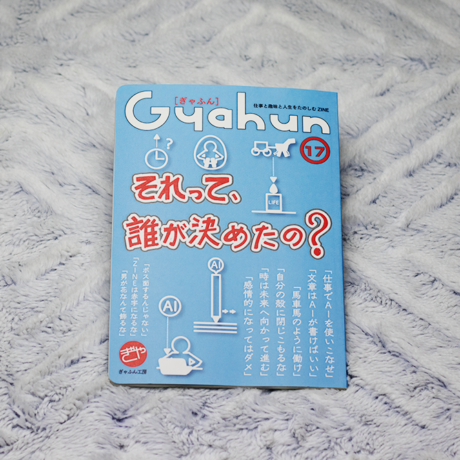
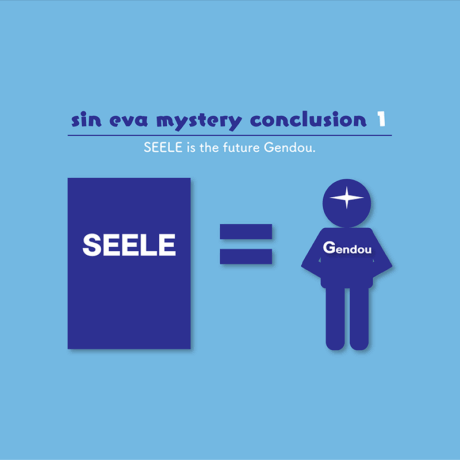
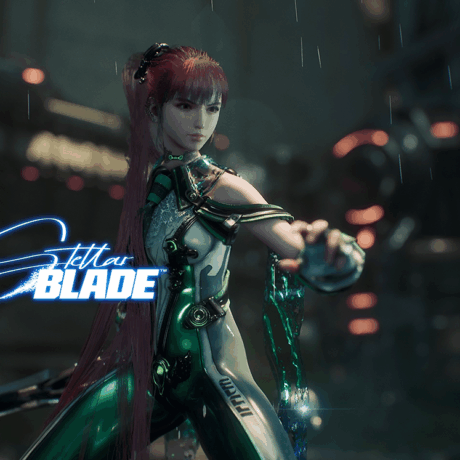

コメント