『The Last of Us Part II』には、前作にはなかった〈仕掛け〉がほどこされている。といっても、目新しいシステムではない。最近レビューしたゲームなどにも取り入れられているものだ。
しかしながら、ありふれたゲームシステムにもかかわらず、これまでにないゲーム体験をプレイヤーは味わうことができる——いや、体験させられてしまう。
今回は、制作陣によって巧妙に仕組まれたこの〈仕掛け〉について考察しながら、本作の魅力を探っていこう。
ここで〈仕掛け〉と呼んでいるゲームシステムがどんなものであるかは、すでに広く知られている。それでも、ネタバレ(=未プレイの人のたのしみを奪う情報公開)を避けるべきだと考えるので、〈仕掛け〉の詳細は語らない。なお、〈仕掛け〉について公式サイトでは触れられていない。やはりプレイ前にこの〈仕掛け〉を知ってしまうと、興が削がれると見なしているようだ。
ゲームのなかで人を殺めることは許されるか?
前作『The Last of Us』をプレイしながら違和感を覚えた部分がある。
それは人間を撃ったり殴ったりしなければならないことだ。
「感染者」と呼ばれるバケモノを撃退していく。これは問題ない。元は人間だったとはいえ、すでに変わり果てた姿となっており、銃を向けることに躊躇はなかった。
一方で、まだ感染していないふつうの人間も登場し、彼ら・彼女らも手にかけなければならない。
これが引っかかった。
もちろん、そもそも相手は敵だ。自分が攻撃しなければ容赦なく襲われて、下手をすれば命を落とす。ゲームオーバーとなり先には進めない。ふつうの人間とはいえ、相手を殺めることがプレイヤーに求められている。
ゲームの舞台は、「感染者」がはびこり社会秩序が崩壊した弱肉強食の世界。人を殺めたとしても、主人公たちが法的な責任を問われることはない。責任を問う機関がすでに存在しないのだから。
だから、殺ってもいい。それはアタマでは理解している。けれど、ココロがブレーキをかけるのだ。
「虚構の世界とはいえ、人殺しをさせるゲームはけしからん!」などと主張したいわけじゃない。
たとえば、本作とおなじノーティドッグ社のつくった『アンチャーテッド』シリーズ。やはり銃などで敵を排除していく局面がある。「排除」とはすなわち「殺し」だ。だが、そこに葛藤は生まれなかった。
たとえるなら、縁日の射的ゲームで、人の姿が描かれた的に弾を当てる。的に描かれた人に対して「撃ったら痛いかな」「死ぬかもしれない」「残された家族はどうなる?」などと考えないのとおなじだ。
『アンチャーテッド』なら平気なのに、『The Last of Us』では悩むのはなぜか? 『The Last of Us』が真正面から〈生〉や〈死〉に向き合っているゲームだからだろう。
それでも、前作は「人を殺す」ことに対して無自覚であったように思う。「しょせんはゲームのなかの世界」「殺らなければ殺られる弱肉強食の世界」という“言い訳”によってプレイヤーのココロの問題が解決される。そんなふうに制作陣は考えていたのだろう。
だが、それは詭弁。本質をはぐらかす愚行——そんな反省があったかどうかはわからない。あろうことか、前作で棚上げにしていた「ゲーム内殺人」。本作ではそこにスポットを当ててきた。そうすることで、プレイヤーのココロを巧みにコントロールしようとしてきたのだ。
そこが、本作の魅力を読みとく最大のポイントとなる。
「これはゲームだから」はプレイヤーの自己欺瞞
本作『The Last of Us Part II』のテーマが「復讐」であることはよく知られている。「復讐」とは、とどのつまり「殺人」だ。「復讐」というお題目を設定することによって、前作のような「ゲーム内殺人」の問題、それによって生まれるプレイヤーのココロの葛藤を解決している——と、当初は思った。あながち的外れでもない。そういう意図もあるのだろう。
しかしながら、制作陣の本意はそこにはない。そのことがあきらかになるのは、本作の中盤だ。
ここで、冒頭で述べた〈仕掛け〉が真価を発揮する。
これまで主人公の行なってきた“蛮行”に、プレイヤーはあらためて目を向けざるを得なくなるのだ。
本作が映画や小説であったならば、どれほどよかっただろう。まだ救いがある。なぜなら、“蛮行”であろうとそうでなかろうと、あくまで虚構の世界のキャラクターが“勝手に”やったことだからだ。表現の受け手が主人公に共感したり、あるいは反感を持ったりすることはあっても、しょせんは他人事にすぎない。
だが、本作はゲーム。主人公の行ないのすべてはプレイヤーの操作による結果だ。
「ゲームの仕様だから」「そうしなければゲームが進まないのだ」などと開きなおることはできる。しかし、それは大いなる欺瞞であるとすぐに自覚する。責めているのはほかの誰でもない自分自身だ。自分に対して申し開きをするしかない。
押し寄せる後悔の念。自分ではどうすることもできない動揺。自分自身に対する“言い訳”は、かき消されていく。いくら言い繕っても、虚しさしか生まれない。
まさしく映画や小説では味わうことのできないゲームならではの体験。しかも、こんな目に遭わされたゲームは過去にも存在しなかった。
「ゲーム内殺人」にプレイヤーの意識を向けさせるため、ムービーのセリフや劇中で手に入る文書を利用する方法もあった。本作の制作陣はそうしなかった。「ゲーム内殺人」になにか道徳的な示唆を与えようとしているわけではない。「ゲーム内殺人」が善いか悪いかを問うているわけではない。プレイヤーを咎めようとしているわけではないからだ。
あくまでプレイヤーにまったく新しいゲーム体験を提供することが至上の目的。だからこそ、セリフを聞かせたり資料を読ませたりするのではなく、実際にプレイヤーの手を汚させたのだ。
『The Last of Us Part II』はホラーゲームなのか?
本作のジャンルはなんだろう? ホラー好きがプレイしそうなゲームなので、「ホラー」に分類してもよさそうだが、公式では「その他」となっている。
前述のように、新しいゲーム体験を提供しているのだから、「ホラー」の枠にはおさまらないのはたしかだ。あるいは、ゲームのジャンルなんか制作陣は「どうでもいい」と考えているのかもしれない。
プレイヤーにとっては、ゲームのジャンルは重要だ。ゲームを購入する際の判断基準になるし、どういう気持ちでプレイすればよいか、参考にもしたいからだ。
本作をプレイすると、ココロになにが生まれるか? 恐怖? なるほど「感染者」と対峙する際は、たしかに恐怖を覚える。その意味では、「ホラー」のレッテルを貼ってもいいのかもしれない。
ただし、「感染者」がおよぼす恐怖は限定的だ。有名なゾンビゲームなどに慣れ親しんできた猛者ならば、そこまで脅威ではない、と虚勢を張ることはできる。
むしろ本作のエッセンスとなるのは、「殺人」によって生まれる後悔の念。後味の悪さ。なんともいえぬ不条理。プレイヤーのココロの生まれるのは、そういったものだ。
そんなマイナスの感情を引き出され、本作のプレイヤーは困惑する。戸惑い、苦悩する。人によっては受け入れられないかもしれない。快楽を求めてゲームをプレイしているはずなのに、不快感を催すのだから。その不快感を“攻撃”に転化させる人もいるだろう。たとえば、ゲームに低評価を下す。自分が不快な想いをしているのは、ゲームの出来が悪いせいだ。そう考えないとココロの平穏を保てない。
いつしか、ゲームに対する悪意ある評価は、本作の主人公が抱いた「復讐心」と奇妙な相似形を描いていることに気づかされる。ココロの平穏を得る口実としての「復讐心」と「攻撃心」。ゲームのキャラクターとプレイヤーのココロは見事に融合していく。これこそがゲームならでは。映画や小説では、ここまで虚構の世界の住人と表現の受け手のココロが融合することはない。
本作を「ホラー」に分類することで、われわれは「ホラー」の真の意味を知ることになる。「ホラー」ゲームとは
〈現実世界で忌避したい感情を否応なしに擬似体験させられるゲーム〉
なのだ。
作品が酷評されるリスクを冒してまで、本作の制作陣は新しいゲーム体験を提供することにこだわった。「新しい」という意味で、本作のジャンルは「その他」。一方で、プレイヤーにマイナスの感情を覚えさせる点で、本作はやはり「ホラー」でもある。
本作をプレイして生まれる“不快感”は、あまりに出来がよすぎることによるもの。前作以上の傑作だからこそ、「これ以上プレイしたくない」と思ってしまうわけだ。
©2020 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Naughty Dog, LLC.
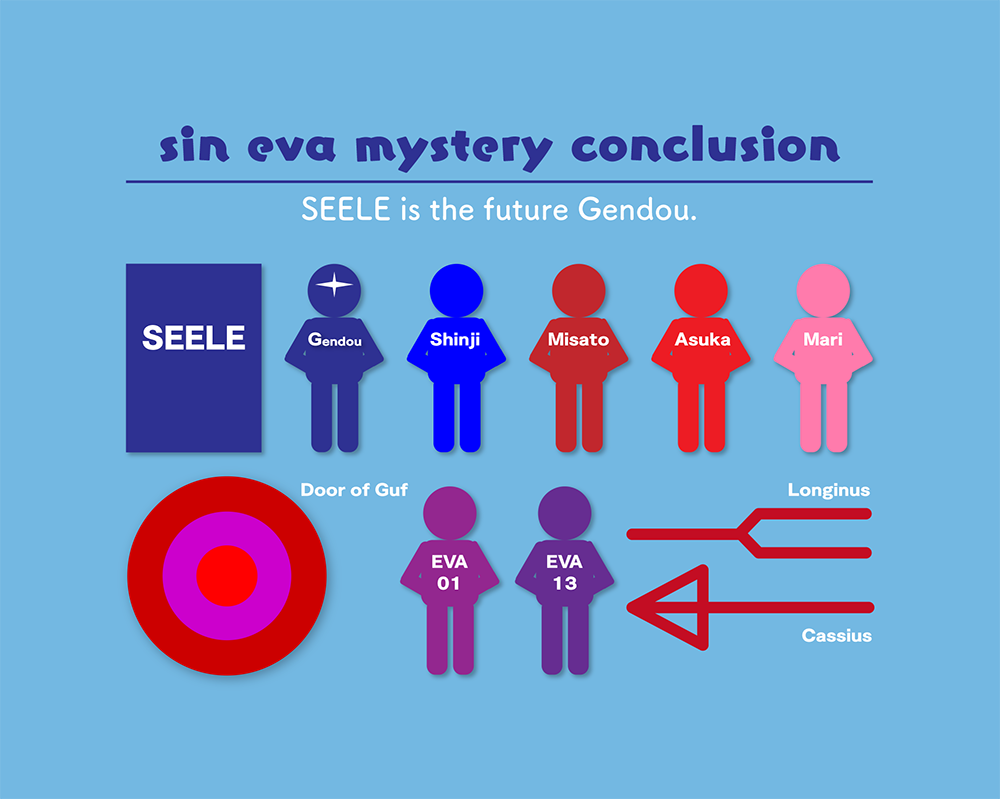


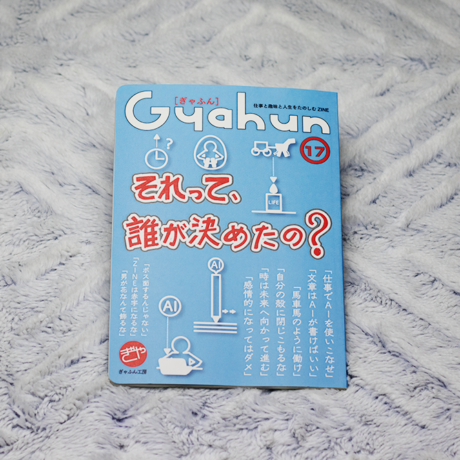
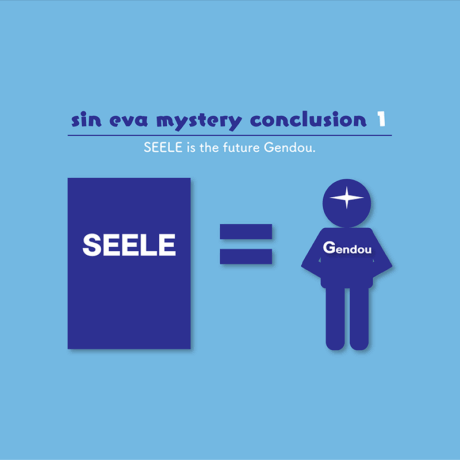
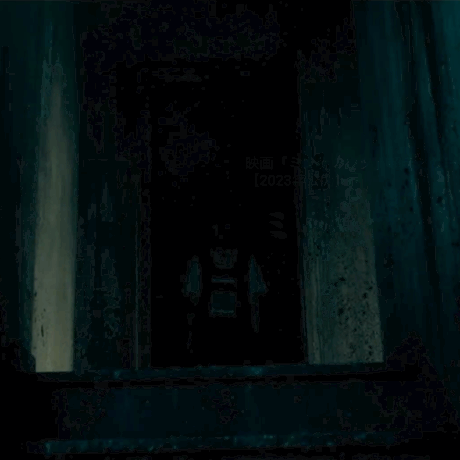


コメント